プロスタサイクリンとプロスタグランジンの違い
プロスタサイクリンの半減期は3分ですが、他のプロスタグランジンより不安定です
プロスタサイクリンの化学構造とプロスタグランジンとの関係性
プロスタサイクリン(prostacyclin)は、プロスタグランジンI2(PGI2)とも呼ばれる物質です。これは単なる呼び名の違いではなく、化学構造に由来する命名なのです。シクロペンタン環にエノールエーテル構造を有することから「プロスタサイクリン」と名付けられました。
つまり、プロスタサイクリンはプロスタグランジンファミリーの一員です。
プロスタグランジンというのは、アラキドン酸カスケードの代謝系で合成される生理活性物質の総称で、20種類以上の種類が報告されています。これらは環構造や側鎖部の二重結合の違いによって分類されており、PGD2、PGE2、PGF2α、PGI2(プロスタサイクリン)、そしてトロンボキサンA2(TXA2)などがあります。それぞれが異なる受容体に結合し、異なる生理作用を発揮するのです。
プロスタサイクリンは、他のプロスタグランジンと比較して特徴的な環構造を持っています。一般的なプロスタグランジンが単純なシクロペンタン環を持つのに対し、プロスタサイクリンはエノールエーテル構造が付加された特殊な環構造を持つのです。この構造的特徴が、プロスタサイクリンの強力な血小板凝集抑制作用と血管拡張作用につながっています。
アラキドン酸からの合成経路を見ると、まずシクロオキシゲナーゼ(COX)によってPGG2、PGH2が生成されます。このPGH2が共通の前駆体となり、各組織に存在する特異的な合成酵素によって各種プロスタグランジンに変換されるのです。プロスタサイクリンの場合は、PGIシンターゼ(プロスタサイクリンシンターゼ)という酵素によってPGH2から変換されます。
トーアエイヨー医療関係者向けサイトでは、プロスタサイクリンの合成経路と代謝の図解が詳しく掲載されています
プロスタサイクリンの半減期と分子安定性の臨床的意義
プロスタサイクリンは化学的に極めて不安定な物質として知られています。24℃の中性水溶液中では半減期約10分、37℃のpH7.4水溶液中では半減期約3分で、6-keto-PGF1αという不活性代謝物に分解されてしまいます。この短い半減期は臨床応用において大きな課題となっているのです。
どういうことでしょうか?
半減期3分というのは、血中に投与されたプロスタサイクリンの半分が、わずか3分で効力を失うということです。例えば、100単位のプロスタサイクリンを投与しても、3分後には50単位、6分後には25単位しか残りません。これは市販のペットボトルのお茶(500ml程度)を開封してから飲み切るまでの時間よりもはるかに短い時間です。
この極端な不安定性には、分子構造が関係しています。エノールエーテル構造は、水溶液中で容易に加水分解されやすい構造なのです。
特に酸性条件下では急速に分解が進みます。
このため、天然のプロスタサイクリン(エポプロステノール)を医薬品として使用する場合は、持続静注による投与が必要となり、投与方法が制限されるという問題があります。
治療の現場では、この不安定性を克服するため、化学構造を改変した安定なプロスタサイクリン誘導体が開発されています。
ベラプロストナトリウムは経口投与可能なPGI2誘導体で、血中濃度のピークが投与後約0.5~1時間、半減期は約1時間と、天然のプロスタサイクリンよりはるかに安定です。トレプロスチニルは半減期約4時間、さらに長時間作用型のONO-1301では半減期5.6時間という報告もあり、投与間隔を延ばすことができます。これらの誘導体は、プロスタノイド骨格の一部を改変することで、15-ヒドロキシプロスタグランジンデヒドロゲナーゼによる代謝分解を受けにくくしています。
プロスタサイクリンの受容体と作用機序の特異性
プロスタサイクリンは、IP受容体(プロスタサイクリン受容体)と呼ばれる特異的なGタンパク質共役型受容体に結合して作用を発揮します。この受容体は、他のプロスタグランジン受容体とは異なる特徴を持っているのです。
IP受容体はGαsタンパク質に共役しており、受容体が刺激されるとアデニル酸シクラーゼが活性化されます。その結果、細胞内のサイクリックAMP(cAMP)濃度が上昇し、cAMP依存性プロテインキナーゼ(PKA)が活性化されるのです。血小板では、このシグナル伝達経路が血小板凝集に必要な細胞内カルシウム濃度の上昇を抑制し、強力な抗血小板作用を発揮します。
血管平滑筋細胞においても同様のメカニズムで、cAMPの上昇が平滑筋の弛緩を引き起こし、血管拡張作用をもたらします。
つまり、cAMP上昇が鍵です。
受容体mRNAの発現分布を見ると、胸腺に最も多く、次いで脾臓、心臓、肺に多く発現しています。血管内皮細胞でプロスタサイクリンが産生され、血小板や血管平滑筋細胞のIP受容体に作用するという、局所的な制御システムが存在するのです。
一方、他のプロスタグランジンは異なる受容体に作用します。PGE2には4種類の受容体サブタイプ(EP1、EP2、EP3、EP4)が存在し、サブタイプによって共役するGタンパク質が異なります。EP1とEP3は主に子宮収縮に、EP2は子宮弛緩に、EP4は子宮頸管熟化に働くなど、同じPGE2でも受容体によって正反対の作用を示すことがあるのです。
PGD2はDP受容体に、PGF2αはFP受容体に、トロンボキサンA2はTP受容体に結合します。このように、プロスタグランジンファミリーは多様な受容体を介して、組織特異的な多彩な生理機能を発揮しているということですね。
プロスタサイクリンの産生部位と生理的役割
プロスタサイクリンは主に血管内皮細胞で産生されます。これはプロスタグランジンファミリーの中でも特徴的な産生部位です。血管内皮細胞には、PGIシンターゼという酵素が豊富に存在しており、この酵素がPGH2をプロスタサイクリンに変換するのです。
血管内皮細胞で産生されたプロスタサイクリンは、血液中に放出され、血小板表面のIP受容体に結合します。その結果、血小板のcAMPが上昇し、血小板凝集が強力に抑制されます。同時に、血管平滑筋細胞にも作用して血管拡張を引き起こすのです。つまり、血管内皮細胞は「抗血栓・血管拡張物質」を産生することで、循環動態のホメオスタシス維持に重要な役割を果たしているということです。
興味深いのは、血小板ではトロンボキサンA2(TXA2)という正反対の作用を持つ物質が産生されることです。TXA2は血小板凝集を促進し、血管を収縮させます。血管内皮細胞由来のプロスタサイクリンと血小板由来のトロンボキサンA2のバランスが、生理的な止血と病的な血栓形成の制御に極めて重要なのです。
このバランスが崩れると、血栓症のリスクが高まります。
動脈硬化などで血管内皮細胞が障害されると、プロスタサイクリンの産生が低下します。一方で血小板からのトロンボキサンA2産生は維持されるため、バランスが血栓形成側に傾いてしまうのです。この病態を改善するために、プロスタサイクリン誘導体製剤が治療薬として用いられています。
他のプロスタグランジンの産生部位は多様です。PGE2は多くの組織で産生され、炎症部位では特に産生量が増加します。PGD2はマスト細胞で、PGF2αは子宮平滑筋などで産生されます。このように、プロスタグランジンは産生される組織によって種類が異なり、局所で作用する「局所ホルモン」としての性質を持っているのです。
プロスタサイクリンの医薬品と適応疾患における違い
プロスタサイクリン誘導体製剤は、主に慢性動脈閉塞症と肺動脈性肺高血圧症の治療に用いられています。これらの疾患では、血管の収縮や血栓形成が病態の中心にあり、プロスタサイクリンの血管拡張作用と抗血小板作用が治療効果をもたらすのです。
現在、国内で使用可能なプロスタサイクリン関連薬には、複数の剤型と作用機序の違いがあります。経口薬のベラプロストナトリウムは、慢性動脈閉塞症に伴う潰瘍、疼痛、冷感の改善に、通常1日120μgを3回に分けて食後投与します。原発性肺高血圧症に対しては、より高用量の投与が必要です。
注射剤のエポプロステノール(天然型PGI2)は、肺動脈性肺高血圧症に対して持続静注で使用されます。半減期が極めて短いため、中心静脈カテーテルを留置して24時間持続投与を行う必要があり、患者の負担が大きいという課題があります。しかし、その強力な血管拡張作用は、重症肺高血圧症患者の生命予後を改善することが証明されています。
吸入剤のトレプロスチニルは、肺高血圧症に対して1日4回吸入投与します。吸入により肺血管に直接作用させることで、全身性の副作用を軽減できるのが特徴です。
選択的IP受容体作動薬のセレキシパグは、経口投与可能な非プロスタノイド構造のPGI2受容体刺激薬です。プロスタノイド骨格を持たないため、代謝が遅く、半減期が長いという利点があります。肺動脈性肺高血圧症の治療において、他の治療薬との併用療法が可能です。
副作用として注意が必要なのは?
プロスタサイクリン受容体を介する副作用として、頭痛、下痢、顎痛、筋肉痛、潮紅、悪心・嘔吐が高頻度で認められます。臨床試験では、副作用発現頻度が97.8%から100%という報告もあり、ほぼ全例で何らかの副作用が出現すると考えておく必要があります。特に頭痛は73.0~73.9%と最も高頻度です。
重大な副作用として、出血(脳出血、消化管出血、肺出血、眼底出血)があります。抗血小板作用による出血傾向の増強には十分な注意が必要です。抗凝固薬や抗血小板薬との併用時には、出血リスクがさらに高まるため、慎重な観察が求められます。
プロスタサイクリンとトロンボキサンの拮抗関係から見る臨床的意義
プロスタサイクリンとトロンボキサンA2は、同じアラキドン酸カスケードから産生されながら、正反対の作用を持つ興味深い関係にあります。この拮抗バランスの理解は、抗血小板療法や抗炎症療法の理論的基盤となっているのです。
血小板では、アラキドン酸からCOX(シクロオキシゲナーゼ)によってPGH2が生成され、さらにトロンボキサン合成酵素によってトロンボキサンA2(TXA2)に変換されます。TXA2は血小板凝集を促進し、血管を収縮させる強力な作用を持ちます。半減期は約30秒と極めて短く、すぐにTXB2という不活性代謝物に変換されます。
一方、血管内皮細胞では、同じPGH2からPGIシンターゼによってプロスタサイクリン(PGI2)が生成されます。プロスタサイクリンは血小板凝集を抑制し、血管を拡張させるのです。
この2つの物質のバランスが、血栓形成と出血のバランスを制御しています。
低用量アスピリン療法の理論的根拠は、このバランスにあります。アスピリンはCOX(特にCOX-1)を不可逆的に阻害する薬剤です。血小板は無核細胞のため、一度COXが阻害されると、血小板の寿命(約7~10日)の間、新たなCOXを合成できません。そのため、低用量のアスピリンでも血小板のトロンボキサン産生を持続的に抑制できるのです。
一方、血管内皮細胞は有核細胞なので、COXを再合成できます。そのため、低用量アスピリンでは、血小板のトロンボキサン産生を選択的に抑制し、血管内皮細胞のプロスタサイクリン産生への影響は最小限に抑えられるという理論です。実際には、アスピリンはプロスタサイクリン産生も一部抑制するため、投与量の設定が重要になります。
臨床的には、低用量アスピリン(81~100mg/日)が心筋梗塞や脳梗塞の予防に広く使用されています。しかし、NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)を高用量で使用すると、プロスタサイクリン産生も強く抑制されるため、心血管イベントのリスクが上昇する可能性が指摘されています。プロスタグランジンの種類と作用の違いを理解することは、薬物治療の安全性を確保する上で不可欠ということですね。
日本ペインクリニック学会の医学生向けページでは、NSAIDsとアラキドン酸カスケードの関係が詳しく解説されています
脳科学辞典のプロスタグランジンのページでは、受容体の種類と生理機能が包括的にまとめられています
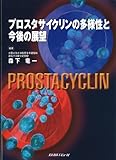
プロスタサイクリンの多様性と今後の展望