制吐剤一覧
制吐剤の作用機序による詳細な分類
臨床現場において、悪心・嘔吐のコントロールは患者のQOLを維持するために極めて重要です。制吐剤を適切に選択するためには、単なる薬剤名の暗記ではなく、それぞれの薬剤がどの受容体に作用し、どの経路で嘔吐中枢を抑制するかという「作用機序」に基づいた分類を理解しておく必要があります。嘔吐反射は、延髄にある嘔吐中枢(VC)が刺激されることで生じますが、その入力経路は多岐にわたり、化学受容体引き金帯(CTZ)、前庭迷路、消化管(求心性迷走神経)、大脳皮質などが関与しています。
主要な制吐剤の分類とターゲットとなる受容体は以下の通りです。
- ドパミンD2受容体拮抗薬
- ベンザミド系(メトクロプラミド、ドンペリドン): 主にCTZのD2受容体を遮断することで制吐作用を示します。メトクロプラミドは血液脳関門(BBB)を通過しやすく中枢作用が強い一方、ドンペリドンはBBBを通過しにくいため、錐体外路症状のリスクが比較的低いとされています。また、消化管のD2受容体遮断によりアセチルコリン遊離を促進し、消化管運動を亢進させる作用も併せ持ちます。
- フェノチアジン系(プロクロルペラジン、クロルプロマジン): 強力なD2遮断作用に加え、ヒスタミンH1受容体やムスカリンM1受容体遮断作用も有しており、広範囲な悪心に対応可能ですが、鎮静作用や錐体外路症状に注意が必要です。
- ブチロフェノン系(ハロペリドール): 強力なD2遮断作用を持ち、特にオピオイド誘発性の悪心・嘔吐や、代謝性要因による悪心に対して緩和ケア領域で頻用されます。
- セロトニン5-HT3受容体拮抗薬(グラニセトロン、パロノセトロンなど)
- 主に消化管粘膜のクロム親和性細胞から放出されるセロトニンが、迷走神経終末の5-HT3受容体を刺激することを阻害します。また、CTZの5-HT3受容体も遮断します。癌化学療法誘発性悪心・嘔吐(CINV)の急性期において中心的な役割を果たします。特にパロノセトロンは第2世代と呼ばれ、半減期が長く受容体親和性が高いため、遅発期の悪心にも一定の効果が期待されます。
- ニューロキニン1(NK1)受容体拮抗薬(アプレピタント、ホスアプレピタント)
- サブスタンスPが結合するNK1受容体を遮断します。特にCINVの遅発期や、高度催吐性リスクの抗がん剤における嘔吐抑制に重要です。延髄の嘔吐中枢におけるNK1受容体遮断が主な作用点です。
- 多元受容体作用抗精神病薬(MARTA)(オランザピン)
- 本来は抗精神病薬ですが、D2、5-HT2、5-HT3、H1、M1など多数の受容体を遮断する「マルチターゲット」な作用を持ちます。これにより、従来の制吐剤で制御困難な悪心や、突出性悪心に対して高い有効性を示します。
- その他
- 副腎皮質ステロイド(デキサメタゾン): 正確な機序は不明ですが、抗炎症作用やBBBの透過性抑制、プロスタグランジン産生抑制などが関与していると考えられています。他の制吐剤と併用することで効果を増強します。
- 抗ヒスタミン薬(ジフェンヒドラミンなど): 前庭迷路からの入力を抑制するため、動揺病(乗り物酔い)や内耳性めまいに伴う悪心に有効です。
医療用医薬品 : オランザピン (オランザピン錠の詳細情報)
制吐薬適正使用ガイドライン第 2 版 – J-Stage制吐剤の癌化学療法ガイドラインとリスク
癌化学療法に伴う悪心・嘔吐(CINV)は、患者にとって最も苦痛な副作用の一つであり、治療の継続性を脅かす要因となります。そのため、日本癌治療学会(JSCO)の「制吐薬適正使用ガイドライン」や、海外のASCO/NCCNガイドラインに基づいた予防的投与が標準化されています。最新の2023年改訂版ガイドラインでは、抗がん剤の催吐性リスクに応じた層別化と、それに基づくレジメン選択がより詳細に規定されています。
催吐性リスク分類と推奨される制吐療法
抗がん剤は、制吐処置を行わなかった場合に嘔吐が発現する頻度によって、以下の4つのリスク群に分類されます。
- 高度催吐性リスク(HEC):頻度90%以上
- 中等度催吐性リスク(MEC):頻度30〜90%
- カルボプラチン、オキサリプラチン、イリノテカンなどが該当します。
- 標準治療:3剤併用療法
- NK1受容体拮抗薬
- 5-HT3受容体拮抗薬
- デキサメタゾン
- カルボプラチンを含むレジメンでは、特にNK1受容体拮抗薬の併用が推奨されます。リスクに応じてオランザピンの追加を検討する場合もあります。
- 軽度催吐性リスク(LEC):頻度10〜30%
- 最小度催吐性リスク:頻度10%未満
- ベバシズマブ、ニボルマブなどの分子標的薬や免疫チェックポイント阻害薬単剤。
- ルーチンの予防投与は行いません。
ブレイクスルー(突出性)悪心への対応
予防投与を行っても発現する悪心・嘔吐に対しては、定期投与されている薬剤とは「異なる作用機序」の薬剤を追加投与(レスキュー)します。ここでは、ドパミン受容体拮抗薬(メトクロプラミド、プロクロルペラジン)や、オランザピンの追加投与が有効です。
制吐療法 | がん診療ガイドライン | 日本癌治療学会
主な抗がん剤の副作用とその対策吐き気・嘔吐について制吐剤の代謝経路と薬物相互作用
制吐剤の選択において、単に効果の強さだけでなく、「代謝経路」と「薬物相互作用」を考慮することは、予期せぬ副作用や他剤の効果減弱を防ぐために不可欠です。特に、複数の薬剤を併用する癌化学療法や緩和ケアの現場では、Cytochrome P450(CYP)を介した相互作用が臨床的に大きな意味を持ちます。これは一般的な検索結果では深く触れられないことが多いですが、専門職としては必須の知識です。
主要な制吐剤の代謝酵素と注意点
- アプレピタント(NK1受容体拮抗薬)とCYP3A4
- オランザピンとCYP1A2
- オランザピンは主にCYP1A2で代謝されます。
- 喫煙の影響: タバコの煙に含まれる多環芳香族炭化水素はCYP1A2を誘導します。そのため、喫煙者ではオランザピンのクリアランスが亢進し、血中濃度が低下する可能性があります。禁煙や喫煙再開時には用量調節の検討が必要になる場合があります。
- ニューキノロン系抗菌薬との併用: シプロフロキサシンなどの強力なCYP1A2阻害薬と併用すると、オランザピンの血中濃度が著しく上昇し、過鎮静や副作用のリスクが高まります。
- ドンペリドンとCYP3A4
- 5-HT3受容体拮抗薬の代謝
- 第1世代(グラニセトロンなど)の多くはCYP3A4で代謝されますが、パロノセトロンは主にCYP2D6で代謝され、一部CYP3A4やCYP1A2も関与します。CYP2D6には遺伝多型が存在するため、個体差が生じる可能性がありますが、パロノセトロンは消失半減期が長く、臨床的な影響は比較的少ないとされています。
相互作用マネジメントの視点
ポリファーマシーになりがちな高齢者や癌患者において、制吐剤を追加する際は必ず「現在服用している薬剤の代謝経路」を確認する必要があります。例えば、CYP3A4阻害作用を持つ薬剤を服用中の患者にドンペリドンを安易に処方することは避けるべきですし、ワーファリン服用患者にアプレピタントを開始する際は医師への注意喚起が必要です。
ドンペリドンの「使用上の注意」の改訂について(PMDA)
薬物相互作用 – 日本医療薬学会妊婦や小児への制吐剤の適応と注意点
妊婦や小児への制吐剤投与は、安全性への配慮が最優先される領域です。特に2025年には、長年の常識を覆す重要な添付文書改訂が行われました。
妊婦への適応:ドンペリドンの禁忌解除(2025年)
長らく、ドンペリドン(ナウゼリン等)は「動物実験での催奇形性作用の報告」等を理由に、妊婦または妊娠している可能性のある女性に対して禁忌とされていました。しかし、以下の背景から2025年4月、厚生労働省およびPMDAの検討を経て、ついに禁忌指定が解除されました。
- 疫学データの蓄積: 国内外の膨大な使用成績調査において、ヒトにおける催奇形性リスクの上昇は認められなかった。
- 臨床現場のニーズ: つわり(妊娠悪阻)に対して使用できる薬剤の選択肢が限られており(メトクロプラミド等に限られていた)、治療上の有益性がリスクを上回ると判断された。
これにより、妊娠中の悪心・嘔吐に対して、メトクロプラミド(プリンペラン)に加え、ドンペリドンも治療選択肢として考慮可能となりました。ただし、あくまで「治療上の有益性が危険性を上回ると判断される場合」に投与するという原則は変わりません。
小児への適応と注意点
小児、特に乳幼児に対する制吐剤の使用は慎重さが求められます。
- 錐体外路症状(EPS)のリスク: 小児は血液脳関門(BBB)が未発達であり、ドパミンD2受容体拮抗薬が中枢に移行しやすい傾向があります。特にメトクロプラミドはEPS(急性ジストニア、眼球上転発作など)の発現リスクが高いため、小児への投与は慎重に行うか、可能な限り避ける傾向にあります。ドンペリドンはBBBを通過しにくいためメトクロプラミドよりは安全とされていますが、過量投与によるEPSや痙攣の報告があるため、1歳以下の乳児には特に用量への注意が必要です。
- 自家中毒(周期性嘔吐症): 小児特有の病態であり、制吐剤だけでなく、輸液による補正やブドウ糖投与が優先されるケースも多々あります。
吐き気止めに使われる薬・ドンペリドンの”妊婦禁忌”解除へ(国立成育医療研究センター)
令和7年度第2回薬事審議会 医薬品等安全対策部会資料緩和ケアにおける制吐剤の選択
緩和ケア領域では、抗がん剤による悪心だけでなく、オピオイド、消化管閉塞、便秘、脳転移、代謝異常など、多種多様な要因が混在します。ここでは「とりあえずプリンペラン」ではなく、病態生理に基づいた受容体ターゲットの選定が求められます。
病態別アプローチ
- 消化管運動不全(Gastric Stasis)
- 原因:胃不全麻痺、腹水による圧迫、自律神経障害など。
- 病態:胃内容物の停滞により、迷走神経求心路が刺激される。
- 推奨薬: 消化管運動機能改善薬(プロキネティクス)。
- メトクロプラミド、ドンペリドン。
- これらはD2受容体遮断によりアセチルコリン遊離を促し、胃排出を促進します。
- 化学受容体引き金帯(CTZ)の刺激
- 原因:オピオイド開始時、高カルシウム血症、尿毒症、薬物代謝産物。
- 病態:血中の催吐物質がBBB外のCTZ(D2受容体豊富)を刺激。
- 推奨薬: 中枢移行性のあるD2受容体拮抗薬。
- ハロペリドール:少量(0.5〜1.5mg/日程度)で強力な制吐効果を示し、鎮静などの副作用も比較的少ない。
- プロクロルペラジン:D2に加えヒスタミンH1遮断作用もあり有効。
- オランザピン:難治性の場合に有効。
- 消化管閉塞(悪性腸閉塞:MBO)
- 原因:腫瘍による腸管の物理的閉塞。
- 禁忌・注意: 消化管運動を亢進させるメトクロプラミドやドンペリドンは、閉塞部位より口側の内圧を高め、腹痛や穿孔を誘発する恐れがあるため原則禁忌です。
- 推奨薬: 消化管分泌を抑制し、運動を抑制する薬剤。
- 脳転移・脳圧亢進
- 前庭障害・体動時の悪心
- 原因:オピオイドによる前庭感受性亢進など。
- 推奨薬: 抗ヒスタミン薬(ジフェンヒドラミンなど)や抗めまい薬(ベタヒスチン)。
緩和ケアにおいては、「何が嘔吐スイッチを押しているか」を推論し、そのスイッチ(受容体)をピンポイントでブロックする戦略が、不必要な多剤併用を防ぎ、効果的な症状緩和につながります。
緩和ケアにおける悪心・嘔吐のガイドライン推奨概要
緩和ケア 薬物療法マニュアル
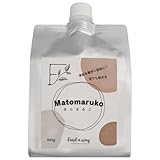
【find a way】液体を凝固して可燃ゴミとして処理できる日本製 約160回分「まとまるこ」凝固剤 非常用 災害用 簡易 携帯 トイレ 大便用 女性用 交通渋滞 車中泊 長距離 運転 BBQ なべ料理・カップ麺残り汁の処理に アウトドアのお供に キッチン・台所 排水処理を簡単に 防災グッズ
