腎アミロイドーシス 病理
腎アミロイドーシス 病理の光顕所見と沈着分布
腎アミロイドーシスの病理で最初に意識したいのは、「腎臓のどこに沈着するか」で、糸球体・血管壁・尿細管基底膜・間質と、あらゆる構造に沈着しうる点が特徴です。腎アミロイドーシスガイドライン2020でも、糸球体・尿細管間質・血管壁と全構造に沈着し得ること、さらに前駆蛋白型により主座が偏ることが整理されています。
光顕では、糸球体メサンギウム領域と糸球体基底膜が主要な沈着部位で、メサンギウムに多量沈着すると結節性病変(nodular lesion)を呈し、基底膜沈着では基底膜肥厚が目立ちます。特に基底膜側の沈着が束状構造を作る“spicula”は、ネフローゼと結びつきやすい形態の一つとして言及されています。
一方で、腎間質沈着は線維化と見分けにくく、PASなどの一般染色だけでは見落としやすい点が実務的な注意点です。糸球体で派手に見えない症例ほど、血管壁や間質を丁寧に走査し、弱い沈着を拾いにいく姿勢が診断精度を左右します。
腎アミロイドーシスは「典型=ネフローゼ」という先入観が強いのですが、病理分布が血管や間質寄りの症例では蛋白尿が乏しいこともあり、臨床像と組織の“沈着主座”が必ずしも一致しない点が落とし穴になります。ガイドライン2020でも、尿細管・間質・細小血管への沈着が主体だと蛋白尿が乏しく腎機能障害が前面に出ることがある、と注意喚起されています。
腎アミロイドーシス 病理のCongo redとDFSと偏光
腎アミロイドーシスの病理診断で、沈着の証明に使う基本がCongo red染色(またはDFS染色)です。ガイドライン2020では、Congo red/DFSで沈着部位が橙赤色に染まり、偏光顕微鏡下でアップルグリーンの偏光性を示すことが典型所見として明確に書かれています。
日本の現場ではDFS(Direct Fast Scarlet)が比較的使われやすく、ガイドライン2020でも「Congo redより染色性が安定しているためDFSが好まれる」一方で、過染性への注意が必要とされています。つまり、染色が“うまく見える”ほど、背景や非特異染まりを拾ってしまい、逆に診断がブレるリスクがあるということです。
ここで重要なのは、染色の色味だけで判断しないことです。Congo red/DFSは、橙赤色の領域がそのままアミロイドとは限らず、偏光でのアップルグリーン確認が診断の芯になります(特に沈着が少ない、あるいは弱陽性のときほど)。
意外に実務で効くポイントとして、「糸球体が陰性っぽいから否定」としないことが挙げられます。沈着が血管壁に偏る例、間質が主体の例、糸球体のごく局所にしかない例では、切片の取り方や観察視野で見え方が大きく変わります。したがって、偏光観察は“全体をスキャン”する運用が安全です。
また、国際的にはCongo redが標準である一方、日本では代用としてDFSが頻用されているという背景も、日腎会誌の総説で整理されています。外部施設コンサルトや多施設研究では、染色法の違いが所見共有の壁になることがあるため、「何染色で、どう判定したか」をレポート上で明確化することは地味ですが重要です。
腎アミロイドーシス 病理の免疫染色とアミロイド蛋白同定
腎アミロイドーシスの病理で、沈着を証明した次に必須になるのが「前駆蛋白の同定(タイピング)」です。ガイドライン2020では、AL型では沈着部位にκまたはλがsingle predominant(一側有意)に反応することが多い一方、抗体によっては十分な反応が得られにくいこともある、と現場感のある注意が書かれています。
AA型、AFib型、ATTR型などは、それぞれの前駆蛋白に対する抗体で免疫染色を行い陽性反応を確認することが病理診断として望ましい、とガイドライン2020に明記されています。つまり、単に“アミロイド陽性”で止めず、できる限り病型へ落とすことが治療方針に直結します。
ただし、免疫染色には本質的な限界があります。ガイドライン2020では、前駆蛋白の断片化や立体構造変化で抗体反応が損なわれ偽陰性となること、非特異的に陽性所見を呈することも少なくないこと、市販抗体では同定が困難な例があることが説明されています。上位施設(Mayo clinic)でも免疫組織化学で同定できない例が一定割合ある、というデータも示されており、“免疫染色が陰性=その型ではない”と短絡しない態度が求められます。
臨床側に伝えるべきメッセージは、「タイピング不能のまま治療を始めるリスク」です。例えばALとAAでは治療戦略がまったく異なり、ALなら形質細胞クローンを叩く治療、AAなら炎症制御(SAA抑制)が中核になります。病理レポートでは、現時点の同定結果だけでなく、「同定の信頼度」「追加検査(後述の質量分析など)の必要性」まで含めて返すと、医療チーム全体の意思決定がブレにくくなります。
腎アミロイドーシス 病理の電子顕微鏡と8~15nm
腎アミロイドーシスの病理では、電子顕微鏡(電顕)が“確信度を上げる”重要な武器になります。ガイドライン2020では、電顕でアミロイド沈着部位を高倍率観察すると、約径10nmの細線維が集合する特徴的所見が得られると説明されています。
日腎会誌の総説でも、電顕で8~15nmの線維構造を呈することがアミロイド線維の特徴としてまとめられています。弱いCongo red/DFS、あるいは光顕で「それっぽいけれど決めきれない」ケースで、電顕が最後の一押しになる場面は少なくありません。
ただし、電顕にも落とし穴があり、ガイドライン2020では細線維が非常に密に集合していると、線維構造を観察しにくいことがあるとされています。つまり、電顕で“見えない”こと自体が直ちに否定にはならず、標本の選び方や観察部位(沈着がある場所を狙えているか)が診断を左右します。
またspicula部位は、細線維が一定方向に束状に集合するなど、他の沈着部位と異なる特徴を持つことがガイドライン2020に記載されています。光顕でspiculaが疑われるなら、その対応部位を電顕で確認することで、膜性腎症のスパイク所見との鑑別など、形態学的な説得力が上がります。
臨床にとっての“意外な有用性”は、電顕が単にアミロイド確認に留まらず、「沈着様式(糸球体、基底膜、血管、尿細管間質)」の理解を助け、症候(ネフローゼか、腎機能低下主体か)との整合性を考える材料にもなる点です。病理カンファレンスでは、光顕+免疫+電顕の三点セットでストーリーを組むと、診療科間の誤解が減ります。
腎アミロイドーシス 病理の独自視点:質量分析と診断戦略
検索上位の説明では「質量分析は有用」で終わりがちですが、現場の診断戦略としては“いつ・なぜ質量分析に進むか”を明確にすることが重要です。ガイドライン2020のCQ-3では、臨床的・組織学的に腎アミロイドーシスが示唆されるのに免疫組織化学で同定困難な症例に対して、質量分析法の実施を推奨すると書かれています。
ガイドライン2020が具体的に示しているのは、レーザーマイクロダイセクションで沈着部位を回収し、LC-MS/MSで蛋白同定する流れです。さらに、免疫染色が偽陰性になり得る背景(断片化・立体構造変化・非特異反応・抗体の限界)が丁寧に説明されているため、「免疫染色が決め手にならないのは珍しくない」という前提で診断アルゴリズムを組み立てられます。
ここで意外に見落とされるのが、質量分析は“最後の手段”というより「治療の方向性を決めるための手段」だという点です。ガイドライン2020では、免疫組織化学で同定できなかった症例の一部でLC-MS/MSによりAL、AA、ALECT2、AFibなどが同定された報告が紹介されており、同定結果がそのまま臨床の分岐になります。つまり、曖昧な免疫染色のまま“経験的にAL扱い”などをすると、不要な化学療法や、逆に必要治療の遅れにつながります。
さらに、臨床現場で効く“独自視点”として、病理レポートの書き方があります。免疫染色が非典型の場合、単に「κ/λ陰性」などと短く書くのではなく、(1)沈着の確実性(Congo red/DFS+偏光、電顕の裏付け)、(2)免疫染色の限界による不確実性、(3)質量分析適応の提案、をセットで記載すると、主治医が次の一手を選びやすくなります。診断は病理部門だけで完結せず、臨床検査(FLC、免疫固定法、炎症指標)との統合で確定するため、“検査計画まで含めた病理診断”がチーム医療での価値になります。
腎アミロイドーシスガイドライン2020(病理、免疫染色、質量分析のCQがまとまっている)
腎アミロイドーシスの病理・診断全体像(Congo red/DFS、免疫染色、LC-MS/MSの位置づけ)
日腎会誌の総説(Congo red/DFS、電顕8~15nm、LC-MS/MSの診断アルゴリズム、病理分類の整理)
診断と分類(Congo red/DFS・偏光、電顕所見、LC-MS/MS、病理分布パターン)
アミロイド腎症と Monoclonal Immunoglobulin Deposition Disease(MIDD)(PDF)
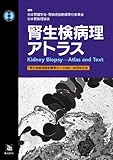
腎生検病理アトラス
