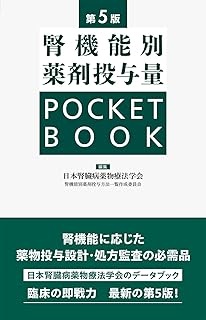睡眠障害の種類と原因について
睡眠障害とは、睡眠に何らかの問題がある状態を指します。睡眠は心身の回復、記憶の定着、免疫機能を強化する重要な役割を担っており、睡眠が障害されると日中の活動に支障をきたし、心身の健康に悪影響を及ぼします。現代社会では睡眠障害が増加傾向にあり、日本人の2割以上が慢性的な不眠に悩み、1割以上が日中の慢性的な眠気(過眠)に悩んでいるとされています。
睡眠障害の種類は多岐にわたり、現在の国際診断分類では67もの病名が存在します。これらは症状面から大きく「不眠」「過眠」「睡眠のリズムがずれる」「寝ぼける」の4タイプに分類できます。どのタイプであっても、日中の眠気や意識水準の低下によって注意力や記憶力などの高次脳機能が障害され、社会生活に支障をきたします。
睡眠障害の不眠症と原因となるストレス要因
不眠症は睡眠障害の中で最も多く見られる症状です。入眠困難(寝つきが悪い)、中途覚醒(夜中に何度も目が覚める)、早朝覚醒(予定より早く目覚めてしまう)、熟睡障害(眠りが浅い)などの症状があり、これらによって必要な睡眠時間が確保できなかったり、睡眠の質が低下したりします。その結果、日中の疲労感、集中力の低下、体調不良、気分の変調などが生じ、生活に支障をきたします。
不眠症の原因としては、以下のようなものが挙げられます。
- 心理的要因
- 眠れないかもしれないという慢性的な不安や緊張
- 仕事や人間関係などによるストレス
- 不眠に対する過度の心配(不眠恐怖)
- 薬剤の副作用
- 身体疾患
- 精神疾患
- 神経疾患
不眠症の治療においては、まず原因となる疾患がある場合はその治療を行うことが重要です。また、生活習慣の改善(睡眠衛生指導)も効果的です。それでも改善しない場合は、睡眠薬などの薬物療法が検討されます。
睡眠障害の過眠症とナルコレプシーの特徴
過眠症とは、夜間に十分な睡眠時間をとっているにもかかわらず、日中に過度の眠気が生じて仕事や学習などに支障をきたす状態を指します。過眠症には主に以下のようなタイプがあります。
ナルコレプシー。
ナルコレプシーは、急に強い眠気に襲われて眠ってしまう「睡眠発作」が特徴的な疾患です。他にも、笑う・驚くなどの感情の変化で突然身体の力が抜ける「情動脱力発作」、眠りに入る際の「睡眠時麻痺(金縛り)」、「入眠時幻覚」などの症状が見られます。
日本人のナルコレプシー有病率は、米国や西欧諸国に比べてやや高いとされています。ナルコレプシーの原因には、脳内で覚醒を維持する物質である「オレキシン(ヒポクレチン)」の低下が関係しています。ナルコレプシー患者の脳脊髄液を検査すると、9割以上の症例でオレキシンの量が測定できないほど低下しており、死後脳の検査ではオレキシンを産生する神経細胞が消失していることが確認されています。
特発性過眠症。
特発性過眠症は、夜に十分な睡眠時間をとっても日中に過度な眠気が続く原因不明の過眠症です。慢性的な睡眠不足との鑑別が重要となります。ナルコレプシーとは異なり、情動脱力発作は見られません。
薬剤による過眠。
抗ヒスタミン作用のある風邪薬や抗アレルギー薬、抗不安薬、抗うつ薬などの薬剤の副作用により日中の眠気が生じることがあります。特に高齢者では薬物の代謝が遅くなるため、作用時間の短い薬でも日中の眠気につながることがあります。
過眠症の診断には、睡眠ポリグラフ検査や反復睡眠潜時検査(MSLT)などが用いられます。治療としては、中枢神経刺激薬や覚醒促進薬などの薬物療法が主体となりますが、規則正しい生活リズムの確立も重要です。
睡眠障害と概日リズム睡眠覚醒障害の関連性
概日リズム睡眠覚醒障害は、体内時計が発する概日リズム(約24時間周期のリズム)と実際の睡眠・覚醒パターンにズレが生じることで、夜間の十分な睡眠がとれなくなる障害です。私たちの体内には、脳の視交叉上核に存在する「体内時計」があり、これが約24時間周期のリズムを刻んでいます。このリズムによって、夜に眠り、日中に活動するという生活リズムが調整されています。
概日リズム睡眠覚醒障害が起こる主な要因としては、以下のようなものがあります。
- 交代勤務障害。夜間に仕事を行う交代勤務者は、体内時計と合わない時間帯に睡眠をとることになります。これにより、十分な睡眠がとれず、日中の眠気や疲労感、消化器症状などが生じます。
- 時差症候群(ジェットラグ)。複数の時間帯を越える飛行機旅行後に、目的地の時間に体内時計が適応できていない状態です。東向きの旅行(時計を進める方向)の方が、西向きの旅行(時計を遅らせる方向)よりも適応が難しいとされています。
- 睡眠相後退症候群。主に思春期から青年期に多く見られ、就寝時刻と起床時刻が通常より2時間以上遅れる状態です。夜型の生活習慣により、睡眠時間帯が後ろにずれることで生じます。
- 睡眠相前進症候群。高齢者に多く見られ、夕方になると眠気が生じ、早朝(2~3時)に目覚めて再入眠できない状態です。加齢とともに増加する傾向があります。
概日リズム睡眠覚醒障害の治療には、光療法(明るい光を浴びることで体内時計をリセットする)、メラトニン製剤の服用、生活習慣の改善(規則正しい睡眠・覚醒スケジュールの維持)などが用いられます。特に朝の光浴は体内時計を調整する上で重要です。
睡眠障害と睡眠時無呼吸症候群の診断方法
睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome: SAS)は、睡眠中に呼吸が一時的に停止する(無呼吸)、または著しく低下する(低呼吸)状態が繰り返し起こる疾患です。この障害は睡眠の質を著しく低下させ、日中の過度の眠気や疲労感、集中力低下などを引き起こします。
睡眠時無呼吸症候群は主に以下の2つのタイプに分類されます。
- 閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)。最も一般的なタイプで、睡眠中に上気道(主に咽頭部)が狭くなったり閉塞したりすることで生じます。睡眠中は筋肉が弛緩するため、舌根が喉の方に落ち込んで気道が塞がれ、いびきや呼吸停止が起こります。
- 中枢性睡眠時無呼吸症候群(CSAS)。脳から呼吸筋への指令が一時的に途絶えることで生じる呼吸停止です。心不全や脳卒中などの疾患に伴って発症することがあります。
睡眠時無呼吸症候群の診断には、以下のような方法が用いられます。
問診と身体所見。
睡眠ポリグラフ検査(PSG)。
睡眠時無呼吸症候群の確定診断に最も重要な検査です。一晩を通して以下の項目を同時に記録します。
- 脳波(EEG)
- 眼球運動(EOG)
- 筋電図(EMG)
- 心電図(ECG)
- 呼吸運動
- 気流
- 動脈血酸素飽和度(SpO2)
- いびき音
- 体位
この検査により、無呼吸・低呼吸指数(AHI:1時間あたりの無呼吸と低呼吸の合計回数)を算出し、重症度を判定します。一般的に、AHIが5以上で軽症、15以上で中等症、30以上で重症と判断されます。
簡易検査(ポータブルモニター)。
自宅で行える簡易的な検査で、PSGほど詳細ではありませんが、スクリーニング目的や、PSG実施が困難な場合に用いられます。
睡眠時無呼吸症候群の治療には、軽症の場合は生活習慣の改善(減量、アルコール・睡眠薬の制限、側臥位での睡眠など)が基本となります。中等症以上の場合は、持続陽圧呼吸療法(CPAP)、口腔内装置、手術療法などが検討されます。
睡眠障害とオレキシン不足の最新研究
睡眠障害、特にナルコレプシーの病態理解において、オレキシン(ヒポクレチン)の発見は大きな転機となりました。オレキシンは1998年に発見された神経ペプチドで、視床下部の外側野に存在する神経細胞から分泌され、覚醒の維持に重要な役割を果たしています。
オレキシンとナルコレプシーの関係。
ナルコレプシータイプ1(情動脱力発作を伴うタイプ)の患者では、脳脊髄液中のオレキシン濃度が著しく低下しています。これは、オレキシン産生神経細胞が選択的に破壊されることによるものと考えられています。実際、死後脳の検査では、オレキシン産生細胞が90%以上減少していることが確認されています。
オレキシン細胞消失のメカニズム。
なぜオレキシン産生細胞が消失するのかについては、自己免疫的な機序が有力視されています。ナルコレプシータイプ1の患者の95%以上がHLA-DQB1*06:02という特定のHLA(ヒト白血球抗原)を持っていることが知られており、これは免疫系の関与を示唆しています。
2009年以降、H1N1インフルエンザのパンデミック後にナルコレプシーの発症率が上昇したことが報告され、特にH1N1ワクチン(特にヨーロッパで使用されたPandemrix)接種後の発症増加が注目されました。これは、インフルエンザウイルスのタンパク質とオレキシン産生細胞の分子構造に類似性があり、分子擬態(molecular mimicry)によって自己免疫反応が誘発された可能性が考えられています。