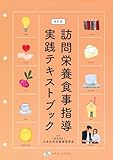居宅療養管理指導を算定できない施設
居宅療養管理指導は、在宅医療を支える重要な介護保険サービスの一つですが、「どこでも算定できる」わけではありません。特に医療従事者が頭を悩ませるのが、利用者が入居している「施設」の種類による算定の可否です。なぜなら、施設によっては医療保険と介護保険の適用範囲が重複したり、すでに施設側のサービスに医療的な管理が含まれていたりする場合があるからです。誤って算定してしまうと返戻(レセプトの差し戻し)や指導の対象となるため、正確な知識が不可欠です。ここでは、まず「算定できない施設」の定義と背景にある考え方を整理し、具体的な施設例を挙げて解説します。
居宅療養管理指導が算定できない典型的なケースとして、まず挙げられるのが「医療機関に該当する場所」です。当然ながら、病院や診療所に入院している患者に対しては、居宅療養管理指導(介護保険)ではなく、医学管理料(医療保険)などが算定されます。しかし、問題は「居住系施設」と呼ばれる場所です。これらは「居宅(自宅)」とみなされる場合と、みなされない場合があります。
厚生労働省の通知やQ&Aに基づくと、養護老人ホーム、軽費老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)などは、原則として「居宅」として扱われ、居宅療養管理指導の算定が可能です。しかし、ここには大きな落とし穴があります。それは「同一建物居住者」の扱いや、施設自体が提供するサービス内容との重複です。
具体的に算定が難しい、あるいは不可となるパターンを見ていきましょう。
- 特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設): 原則として配置医師が健康管理を行う義務があるため、外部の医師による居宅療養管理指導は、一部の例外(末期がん患者への対応や配置医師の専門外の診療など)を除き算定できません。
- 介護老人保健施設(老健): 医師が常駐しているため、外部からの居宅療養管理指導は算定できません。
- 介護医療院: これも医療施設としての性格が強いため、同様に算定不可です。
- 短期入所生活介護(ショートステイ): 利用期間中は、原則として算定できません(ただし、期間が長期にわたる場合の特例等は要確認)。
このように、施設そのものに医師や医療スタッフの配置が義務付けられている場合、二重給付を防ぐ観点から外部からの算定は制限されます。
さらに注意が必要なのは、有料老人ホームやサ高住であっても、「誰が指導を行うか」によって算定単位や可否が変わる点です。例えば、医師が訪問する場合と、訪問看護ステーションの看護師が訪問する場合では要件が異なりますが、居宅療養管理指導は医師、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士等が対象です。特に薬剤師による指導の場合、施設側での服薬管理体制が整っているとみなされれば、算定のハードルは上がります。
参考リンク:厚生労働省による令和6年度介護報酬改定に関する通知等について詳しく記載されています。
また、盲点となりやすいのが「通院困難」という要件の解釈です。施設に入居していても、家族の送迎や介護タクシーを利用して容易に通院できる状態であれば、訪問診療および居宅療養管理指導の算定要件を満たさない可能性があります。施設側が「協力医療機関への送迎バス」を出している場合などは、通院が可能と判断されるリスクがあるため、個別の状況を慎重にアセスメントする必要があります。
居宅療養管理指導の算定要件と対象者や通院困難
居宅療養管理指導を算定するためには、施設の種類だけでなく、対象者自身の状態や算定要件を厳密に満たす必要があります。医療従事者が最も注意すべきは、「通院が困難である」という要件の解釈と、それを裏付ける根拠の記録です。単に「高齢だから」「施設に入っているから」という理由だけでは不十分であり、医学的な見地から通院による身体的負担やリスクを評価しなければなりません。
通院困難の定義と判断基準
「通院困難」とは、独力での通院が不可能であり、家族等の介助があっても通院に伴う負担が大きい状態を指します。具体的には以下のようなケースが該当します。
- 寝たきり、またはそれに準ずる状態で、移動にストレッチャーや車椅子が必要であり、頻繁な通院が著しく困難な場合。
- 認知症により、通院環境に適応できず、診察室での待機や移動が困難、あるいは精神的に不安定になる場合。
- 慢性的な疼痛や呼吸不全(在宅酸素療法中など)があり、移動自体が病状悪化のリスクとなる場合。
- 免疫機能が著しく低下しており、外出による感染リスクが極めて高い場合。
施設入居者の場合、施設スタッフのサポートがあれば通院できるのではないか、と保険者(市町村)から問われることがあります。この際、「施設の人員配置上、通院介助に割けるスタッフがいない」という理由は、介護保険上の「通院困難」の医学的理由にはなりません。あくまで「患者本人の身体的・精神的状況」が判断の主軸となります。これをカルテやケアプランに明記しておくことが、算定を守るための防御策となります。
要介護認定とケアプランへの位置づけ
居宅療養管理指導は介護保険サービスであるため、利用者は要介護認定(要支援1・2、要介護1~5)を受けている必要があります。要支援者の場合は「介護予防居宅療養管理指導」として算定されます。
重要なのは、このサービスがケアマネジャー(介護支援専門員)の作成するケアプラン(居宅サービス計画書)に位置づけられていなくても、算定自体は可能(区分支給限度基準額の対象外であるため)という特殊な性質を持っている点です。しかし、だからといってケアマネジャーへの報告を怠ってよいわけではありません。むしろ、「医師や薬剤師等からケアマネジャーへの情報提供」こそが、この指導料の核心部分であり算定要件そのものです。
情報提供の必須項目
算定にあたっては、以下の情報をケアマネジャーに提供し、記録に残す必要があります。
- 利用者の心身の状況(病状の安定度、バイタルサインの変化など)
- 日常生活上の注意点(食事制限、運動量、入浴の可否など)
- 服薬に関する指導内容(残薬確認、副作用のモニタリング、服薬カレンダーの活用指示など)
- 緊急時の対応方法
これらの情報を文書(報告書)等で提供することが求められます。最近ではICTを活用した情報共有も認められつつありますが、基本的には「ケアプランに反映させるための専門的助言」を行うことが目的です。したがって、「特に変化なし」という定型的な報告だけを続けていると、実地指導などで「指導の実態がない」と指摘される恐れがあります。
参考リンク:日本医師会による介護報酬改定に伴う居宅療養管理指導の取り扱いに関する解説です。
居住系施設における「同一建物」の減算
施設入居者への算定で避けて通れないのが、「同一建物居住者」に対する減算規定です。これは、医師や薬剤師が効率的に複数の患者を訪問できる環境にある場合、報酬単価を下げるという仕組みです。
| 区分 | 対象 | ポイント |
|---|---|---|
| 単一建物診療患者が1人 | 居宅、または施設内でその月、その医師が診療した患者が1人のみ | 通常の算定単位数(最も高い)。 |
| 単一建物診療患者が2~9人 | 同じ建物の居住者で、その月に2~9人を診療 | 単価が下がる。有料老人ホームなどでは一般的。 |
| 単一建物診療患者が10人以上 | 同じ建物の居住者で、その月に10人以上を診療 | さらに単価が下がる。大規模施設への訪問時に適用。 |
| 居住場所が同一 | 養護老人ホーム等に併設された医療機関からの訪問など | 場合によっては算定不可、または大幅な減算。 |
この「人数」は、「その日に訪問した人数」ではなく、「その月に訪問診療・往診を行った同一建物内の患者総数」で判定される点に注意が必要です。例えば、毎週火曜日に3人ずつ、計4回訪問して延べ12人を診たとしても、実人数が3人であれば「2~9人」の区分になります。しかし、別の日にも別の患者を診ていて、月の総患者数が10人を超えれば、全員分の算定が「10人以上」の区分に変わります。この管理が漏れると、過剰請求となってしまいます。
居宅療養管理指導におけるケアマネジャーへの情報提供と連携
居宅療養管理指導の算定において、最も実務的で、かつ不備が指摘されやすいのが「ケアマネジャー(介護支援専門員)への情報提供」です。これは単なる事務連絡ではなく、医療と介護の連携を担保するための法的要件であり、算定の根幹をなすプロセスです。施設に入居している利用者の場合、施設のケアマネジャーが担当することが多いですが、外部の居宅介護支援事業所のケアマネジャーが担当しているケースもあり、連携の構図が複雑になることがあります。
情報提供の質とタイミング
算定要件上、情報提供は「速やかに」行う必要があります。一般的には、訪問診療や指導を行った後、遅くとも月内、あるいは次回のケアプラン更新に間に合うタイミングでの提供が求められます。しかし、現場で評価される(=監査等で問題視されない)のは、その「質」です。
単に「血圧安定、変わりなし」と伝えるだけでは、ケアマネジャーは具体的なケアプランに落とし込むことができません。以下のような具体的な視点での情報提供が求められます。
- 食事・栄養面: 「嚥下機能が若干低下しているため、刻み食への変更を検討してほしい」「脱水傾向が見られるため、水分摂取を1日1000ml目標とし、ゼリー等も活用してほしい」といった具体的な指示。
- 活動・ADL面: 「心不全のコントロールは良好だが、長時間の入浴は心負荷となるため、シャワー浴または短時間の入浴(5分程度)にとどめてほしい」「転倒リスクがある薬剤を追加したため、歩行時の見守りを強化してほしい」といった生活上のリスク管理。
- 服薬管理: 「飲み忘れが増えているため、朝食後の1回法に変更した。施設スタッフによる配薬の徹底をお願いしたい」というような、服薬アドヒアランス向上のための提案。
これらの情報は、ケアマネジャーが作成する「居宅サービス計画書(ケアプラン)」の第1表(総合的な援助の方針)や第2表(生活全般の解決すべき課題・目標・援助内容)に反映されるべきものです。医師や薬剤師からの情報がケアプランに反映され、それに基づいてヘルパーや施設スタッフが動くというサイクルが回って初めて、居宅療養管理指導の意義が認められます。
参考リンク:東京都福祉保健局による居宅療養管理指導の運営の手引きや実地指導のポイントがまとめられています。
「指導」と「診療」の明確な分離
施設への訪問時、医師は「診療(診察・処置・処方)」と「居宅療養管理指導(療養上の助言・管理)」を同時に行うことがほとんどです。しかし、これらは制度上、明確に区別されなければなりません。
- 医療保険(訪問診療料等): 患者の身体に対する直接的な医療行為。
- 介護保険(居宅療養管理指導費): 患者や家族、介護者に対する療養上の管理・指導、およびケアマネジャーへの情報提供。
カルテ記載においても、この2つを分けて記載することが推奨されます。「〇〇の処置を行った」という診療記録とは別に、「〇〇について家族に指導した」「ケアマネジャーへ〇〇の情報をFAXで提供した(送信日:〇月〇日)」といった記述がなければ、居宅療養管理指導を行った証拠としては不十分とみなされることがあります。特に施設においては、施設スタッフへの指示も「介護者への指導」に含まれるため、誰に何を伝えたかを詳細に残すことが重要です。
意外な落とし穴:ケアマネジャーがいない場合
稀なケースですが、利用者が「セルフプラン(自分でケアプランを作成)」を選択している場合や、一時的にケアマネジャーが決まっていない空白期間が生じることがあります。居宅療養管理指導の算定要件には「ケアマネジャーへの情報提供」が必須となっていますが、ケアマネジャーが存在しない場合はどうなるのでしょうか?
この場合、「地域包括支援センター」がその役割を担っていることが多いため、そこへ情報提供を行うことで要件を満たすことができます。あるいは、セルフプランであっても、市町村への届出を行っているはずなので、市町村の介護保険担当課へ確認し、適切な提出先を確保する必要があります。決して「ケアマネジャーがいないから情報提供しなくていい」とはなりません。この点は見落とされがちですが、算定の根拠を失わないために非常に重要なポイントです。
他職種との連携強化(多職種連携)
居宅療養管理指導は、医師だけでなく、歯科医師、薬剤師、管理栄養士、歯科衛生士、看護職員(病院・診療所からの訪問の場合)も算定可能です。施設内では、これらの職種が入り乱れて関わることがあります。
例えば、医師が栄養管理の必要性を感じて管理栄養士に居宅療養管理指導を指示する場合、医師の指示書が必要です。ここで重要なのは、「医師の居宅療養管理指導」と「管理栄養士の居宅療養管理指導」は併算定が可能ですが、それぞれの指導内容と目標が共有されているかという点です。医師が「塩分制限」を指示しているのに、管理栄養士への指示が曖昧で現場が混乱する、といった事態は避けなければなりません。異なる職種間でも情報提供(指示・報告)の記録を残し、チームとして一貫した指導を行う体制が、結果として算定の適正化につながります。
有料老人ホームやサ高住など居住系施設の算定区分と注意点
「施設」と一口に言っても、介護保険法上の扱いは多岐にわたります。特に近年増加している「有料老人ホーム」や「サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)」は、外見上は施設ですが、居宅療養管理指導においては原則として「居宅」として扱われます。しかし、算定区分(単一建物診療患者の人数)や、施設の種類による細かな制約が存在し、ここが請求事務上の最大のボトルネックになりがちです。
特定施設入居者生活介護の指定を受けている場合
有料老人ホームやサ高住の中で、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設(いわゆる「介護付き」)の場合、介護サービスは施設内のスタッフによって包括的に提供されます。しかし、医療については外部の医療機関を利用することが前提となっているケースが多く、居宅療養管理指導の算定が可能です。
ここで注意すべきは、「協力医療機関」との関係です。特定施設は協力医療機関を定める義務がありますが、入居者は必ずしも協力医療機関の医師にかかる義務はありません。入居者が以前からのかかりつけ医による訪問診療を希望する場合、外部の医師が訪問し、居宅療養管理指導を算定することは正当な権利として認められています。
しかし、施設側が「管理の都合上、協力医療機関に統一してほしい」と強く誘導するケースがあり、これがトラブルの元になることがあります。医療従事者側としては、患者の「フリーアクセス権」を尊重しつつ、施設側と円滑な連携を図る必要があります。具体的には、施設スタッフに対して「外部医師が入ることで、夜間の緊急対応はどうなるのか」「処方薬の管理は誰がするのか」といった懸念点を払拭する説明が求められます。
住宅型有料老人ホーム・サ高住(一般型)の場合
これらは制度上、純粋な「住宅」に近いため、外部の居宅介護サービス(訪問介護や訪問看護など)と組み合わせて生活しています。したがって、居宅療養管理指導のニーズは非常に高いエリアです。
ここでの最大の注意点は、先述した「同一建物居住者」の人数計算です。
サ高住などは数十人~百人規模の建物が多く、同じ日に複数の入居者を診察するケースが頻発します。
例えば、あるサ高住にAクリニックの医師が訪問し、同日にB薬局の薬剤師も訪問した場合を考えます。
- 医師の算定:その月にAクリニックがその建物内で何人の患者を診たかで単価決定。
- 薬剤師の算定:その月にB薬局がその建物内で何人の患者に指導したかで単価決定。
つまり、事業所ごとにカウントを行うため、医師は「10人以上」の区分で算定し、薬剤師はまだ患者が少なく「2~9人」の区分で算定する、というズレが生じます。これを混同しないよう、レセプト請求システムの設定を慎重に行う必要があります。
参考リンク:WAM NETによる介護報酬の解釈通知など、実務的な資料が検索できます。
外部サービス利用型特定施設の場合
あまり数は多くありませんが、「外部サービス利用型」の特定施設の場合、ケアプラン作成や安否確認などは施設が行いますが、身体介護などは外部の事業者に委託します。この場合も居宅療養管理指導は算定可能ですが、誰がケアの主導権を握っているかが曖昧になりがちです。
特に、施設スタッフ(特定施設の職員)と、外部の委託先ヘルパー、そして訪問診療医の間で情報共有が滞ると、指導内容が現場に反映されません。このタイプの場合、連絡ノートやICTツール等を活用し、情報共有のハブを明確にしておくことが、適正な算定(実態のある指導)には不可欠です。
短期入所(ショートステイ)における例外規定
原則としてショートステイ中は居宅療養管理指導を算定できませんが、「看取り」が関わる場合や、退所直前の指導など、一部例外的に認められるケースがあります。
例えば、ショートステイ利用中に病状が急変し、自宅に戻って看取りを行うことになった場合、その移行期間に行われる指導については、緊急性や必要性が認められれば算定できる可能性があります(自治体の判断による部分が大きいため、事前の確認が必須です)。
また、ショートステイが30日を超えるような長期滞在となり、実質的に生活の拠点となっている場合も、保険者との協議により算定が認められる余地があります。このように、「原則不可」であっても、患者の利益(適切な医療管理の継続)が損なわれる場合は、柔軟な解釈が可能かを行政に確認する姿勢も専門職には求められます。
医師以外の職種(薬剤師・歯科医師等)による居宅療養管理指導の独自視点
居宅療養管理指導というと、医師によるものが注目されがちですが、実は薬剤師、歯科医師、管理栄養士、歯科衛生士による指導も非常に重要であり、かつ「算定できない施設」や「算定要件」に関して独自の複雑さを持っています。ここでは、検索上位の記事ではあまり深く触れられていない、コメディカル特有の視点と注意点を掘り下げます。
薬剤師による居宅療養管理指導の特殊性
薬剤師の場合、医師の指示に基づいて実施されますが、施設の種類によって算定ハードルが大きく異なります。
特に有料老人ホームやサ高住において、「施設側で服薬管理が行われている場合」の解釈が争点となります。
施設スタッフが薬を預かり、配薬ボックス等で管理して入居者に手渡している場合、「薬剤師による管理は不要ではないか?」とみなされることがあります。しかし、薬剤師の居宅療養管理指導の本質は、単なる「薬のセット」ではありません。
「多剤併用(ポリファーマシー)の解消提案」「残薬調整」「副作用の早期発見」「嚥下能力に合わせた剤形の変更提案」など、専門的な薬学的管理を行っているかどうかが問われます。
独自視点として強調したいのは、「麻薬管理」が必要な患者における薬剤師の重要性です。
がん末期の患者が施設に入居している場合、麻薬(オピオイド)の管理は厳格さが求められます。施設スタッフは医療用麻薬の取り扱いに慣れていないことが多く、保管管理や在庫確認に不安を抱えています。ここで訪問薬剤師が介入し、麻薬の適正管理指導を行うことは、単なる算定以上に、施設側の法的リスクを低減し、患者の安楽な療養生活を支える決定的な役割を果たします。このような「高度な管理」が介入理由であれば、施設の種類に関わらず算定の妥当性が高く評価され、返戻リスクも低くなります。
歯科医師・歯科衛生士による「食支援」としての指導
歯科の居宅療養管理指導は、単なる「歯の治療」の延長ではありません。摂食嚥下機能の評価と、それに基づく「食形態の指導」がメインコンテンツとなります。
施設入居者の場合、誤嚥性肺炎のリスクが常にあります。しかし、施設の厨房や介護スタッフは「どのような食事が最適か」を判断する専門知識が不足していることがあります。
ここで歯科医師や歯科衛生士が介入し、嚥下内視鏡検査(VE)等を実施(または評価)した上で、「ミキサー食ではなく、ソフト食なら食べられる」「とろみの粘度はこの程度が良い」といった具体的な指示を出すことは、利用者のQOL(食べる喜び)に直結します。
算定できないケースとして注意すべきは、「医療保険の訪問歯科衛生指導料」との重複です。同一月に介護保険と医療保険の指導料を併算定することはできません(原則として介護保険が優先)。
また、施設によっては「協力歯科医」が指定されており、往診を行っている場合があります。入居者が別の歯科医を希望する場合、二重診療にならないよう、施設側との調整が必須です。「口腔ケア」は介護スタッフも行いますが、歯科専門職による「専門的口腔ケア」との線引きを記録に残すことが、実地指導対策として重要です。
参考リンク:日本歯科医師会による訪問歯科診療や居宅療養管理指導のガイドラインです。
管理栄養士による指導のニッチな需要
管理栄養士による居宅療養管理指導は、医師の指示が必要ですが、実施できる管理栄養士は「医療機関併設」または「訪問看護ステーション所属(一部要件あり)」などに限られていました(制度改正で薬局所属の管理栄養士も要件を満たせば可能になりつつあります)。
施設において最も盲点となるのが、「特別食(腎臓病食、糖尿病食など)」の提供加算との兼ね合いです。
施設側ですでに栄養管理加算等を算定している場合、外部からの管理栄養士の指導が必要なのか、重複ではないかと問われる可能性があります。
しかし、ここでの独自視点は「移行期の栄養管理」です。
入院から施設へ、あるいは自宅から施設へ移った直後は、環境変化により食欲不振や体重減少が起きやすい時期です。施設側の管理栄養士(配置されていない施設も多い)の手が回らない場合、外部の管理栄養士が介入し、詳細な栄養アセスメントを行い、具体的なメニュー調整や栄養補助食品(ONS)の導入を提案することは非常に有益です。
「施設食が口に合わない」という理由で低栄養になるケースは多々あります。ここで「好みを考慮した代替案」や「補食の提案」を行うことは、施設側では対応しきれないきめ細やかなサービスとして、算定の正当性を強く主張できるポイントです。
結論として、コメディカルによる居宅療養管理指導は、単に「行けば算定できる」ものではなく、「施設側のケアの隙間を埋める専門性」を明確に記録に残すことで、初めて適正に算定できるものです。各職種がそれぞれの専門性を発揮し、かつ施設側のサービスと重複しない「独自の付加価値」を提供し続けることが、厳格化する算定要件をクリアする鍵となります。