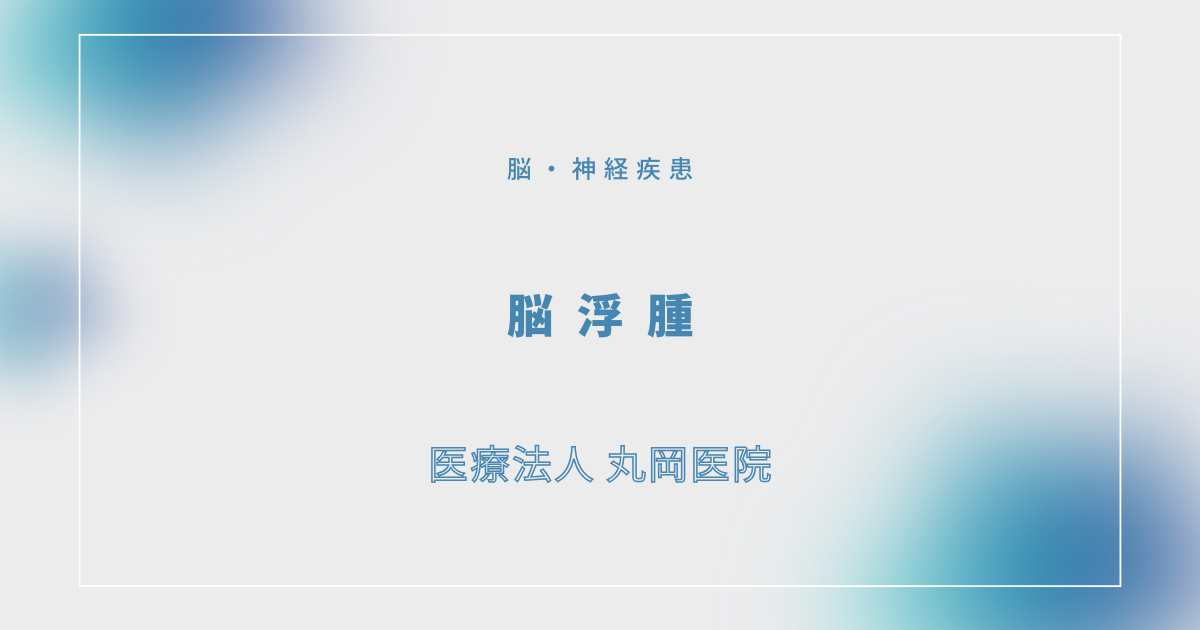脳浮腫ステロイド治療
脳浮腫に対するステロイド適応と効果機序
脳浮腫に対するステロイド療法は、特に腫瘍性脳浮腫において優れた効果を示す治療法です 。副腎皮質ステロイド薬は、抗炎症作用と血管透過性抑制作用により脳浮腫を軽減し、特に腫瘍性脳浮腫において優れた効果を発揮します 。ステロイドの抗脳浮腫効果は、ステロイドの持つ多面的機能が治療効果を生んでいると考えられています 。
参考)https://maruoka.or.jp/brain-and-nerve/brain-and-nerve-disordrs/brain-edema/
腫瘍周辺の血管では、血管内皮増殖因子(VEGF)やその他の炎症性産物により血管透過性が亢進し、間質性血管性脳浮腫が引き起こされます 。ステロイドは、腫瘍細胞のVEGF産生を抑制し、内皮細胞やアストログリア細胞にも作用することで、血管透過性の改善を図ります 。特に脳浮腫が強くなって頭痛や手足の麻痺などさまざまな症状があらわれても、ステロイド治療により脳浮腫が改善して症状が劇的によくなることがあります 。
参考)https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC5136308/
臨床研究では、腫瘍隣接脳は浮腫のため可逆的な乏血状態に陥っており、デキサメタゾンはこれを回復させる効果を持つことが確認されています 。この局所脳血流改善効果により、症状の改善が期待できるのです。
参考)https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.11477/mf.1406205213
脳浮腫治療でのステロイド薬剤選択基準
脳浮腫治療において、鉱質コルチコイド作用の少ないデキサメタゾンやベタメタゾンが一般的に使用されます 。これらの薬剤は、高い抗浮腫効果と比較的少ない電解質代謝への影響から、標準的な治療薬として使用され、2-4週間の投与期間で効果を判定します 。
参考)https://www.jsn-o.com/guideline3/CQ/014.html
デキサメタゾンは、膠芽腫患者の脳浮腫に伴う症状や脳腫脹の治療でしばしば処方される強力な副腎皮質ステロイド剤です 。転移性脳腫瘍の治療では、ステロイド薬は経口薬で、デキサメタゾンやベタメサゾン(リンデロン)が使用されることが多いとされています 。
参考)https://plaza.umin.ac.jp/sawamura/braintumors/meta/
頭蓋内腫瘍による頭蓋内圧亢進がある場合、デキサメタゾン4mg(経口、6~12時間毎)またはプレドニゾン30~40mg(経口、1日2回)により治療が行われます 。ベタメサゾンは潰瘍や糖尿を起すことが少ないため、一部の専門医により愛用されている薬剤もあります 。
参考)https://webview.isho.jp/journal/detail/abs/10.11477/mf.1407204850
薬剤の選択に際しては、消化管出血や糖尿病、易感染性などの合併症に注意しつつ、長期に使用することは避け、経過をみながら適宜漸減・中止を検討することが重要です 。
脳浮腫のステロイド療法における副作用対策
ステロイド治療は効果的である一方で、長期使用には多くの副作用を伴います。主な副作用として、胃十二指腸潰瘍、糖尿病、高血圧、感染症や結核の悪化などがあります 。ステロイド薬を長期間使うことで起こる可能性があるリスクとして、体を病気から守る力(免疫機能)が弱くなる、骨がもろくなる(骨粗鬆症)、糖尿病になる、胃や十二指腸に潰瘍ができる、気分の変化や不眠などの精神的な症状が出るなどが挙げられます 。
参考)https://maruoka.or.jp/brain-and-nerve/brain-and-nerve-disordrs/metastatic-brain-tumor/
副作用は、ステロイド薬をたくさん使うほど、また長く使うほど起こりやすくなります 。一般的な副作用には、皮膚が薄くなり伸展裂創やあざができる、高血圧、血糖値の上昇、白内障、顔面(ムーンフェイス)と腹部の腫れ、腕や脚が細くなる、傷が治りにくい、小児では成長障害などがあります 。
特に注意すべきは、中枢神経系原発悪性リンパ腫が疑われる場合には病理診断前のステロイドの使用は勧められないことです 。また、デキサメタゾンを投与されていた膠芽腫患者では免疫チェックポイント阻害薬投与時の全生存期間が有意に短いという研究結果もあり、免疫療法との併用には注意が必要です 。
参考)https://www.cancerit.jp/gann-kiji-itiran/nousyuyou/post-67676.html
副作用の予防対策として、胃潰瘍予防薬の併用、血糖値のモニタリング、骨密度の定期的な評価、感染症に対する注意深い観察が重要です。
脳浮腫の病態生理メカニズムとステロイド作用点
脳浮腫の発症メカニズムは複数の要因が関与して起こります 。神経細胞が脳梗塞や外傷によって障害されると、細胞機能は低下し、電解質の調節がうまくいかなくなり、その結果、細胞内にナトリウムと水分が過剰に蓄積して浮腫が起こります 。
脳浮腫は主に3つのタイプに分類されます。血管性浮腫は血液脳関門の破綻により血管内から間質への水分漏出で生じ、細胞毒性浮腫は細胞内へのナトリウムと水の過剰蓄積により発生します 。間質性浮腫は脳室系から間質への脳脊髄液の流入により起こります 。
参考)https://kango-oshigoto.jp/hatenurse/article/1833/
ステロイドの作用機序として、グルココルチコイドは腫瘍周辺の浮腫に作用する多様な細胞型に影響を与えます 。具体的には、腫瘍細胞の生存性を低下させ、血管内皮増殖因子(VEGF)の産生を抑制し、内皮細胞とアストログリア細胞にも作用することで抗浮腫効果を発揮します 。
特に腫瘍性脳浮腫では、血管透過性の亢進が主要な病態であり、ステロイドの血管透過性抑制作用が治療の中核となります。脳の炎症という過程により、血管の透過性が増したり、血管の収縮を来したりするため、ステロイドの抗炎症作用が浮腫の改善に重要な役割を果たします 。
脳浮腫ステロイド療法の投与プロトコールと管理法
脳浮腫に対するステロイド投与において、適切な投与方法と期間の設定が治療成功の鍵となります。急性期では予防的にステロイド投与を行うことが多く、年齢、病巣、合併症などで量、期間は千差万別です 。ガンマナイフ治療における浮腫管理では、超急性期浮腫は照射後数時間~24時間で収束し、急性期は数日から数週間継続し、ピークは1-2週間続くことが多いとされています 。
参考)http://www.takai-hp.com/lib/pdf/gamma_tsushin_vol37.pdf
転移性脳腫瘍では、神経症状を呈する腫瘍周辺の浮腫に対してはステロイドや浸透圧利尿薬の使用が推奨されます(推奨グレードB)。一方、明らかな頭蓋内圧亢進や神経症状がない状態では、ステロイドや浸透圧利尿薬の使用は勧められません 。
投与プロトコールでは、デキサメタゾン4mg(6-12時間毎、経口)またはプレドニゾン30-40mg(1日2回、経口)が標準的な用量として用いられます 。しかし、ステロイドの効果は一時的なものであり、腫瘍が進行した場合にはステロイドが増量されることもあります 。
参考)https://ganjoho.jp/public/cancer/brain_adult/treatment.html
重要な管理ポイントとして、長期に使用することは避け、経過をみながら適宜漸減・中止を検討することが挙げられます 。症状があるようでしたらステロイドの内服が必要になりますが、多くは無症状であることも知られています 。治療効果の評価では、2-4週間の投与期間で効果を判定し、MRIによる画像評価と併せて臨床症状の改善を総合的に評価することが重要です 。
参考)https://tguc.jp/aboutgu/index.html
参考文献情報については以下のリンクで詳細な治療ガイドラインと最新の研究報告が確認できます。
日本脳神経外科学会による転移性脳腫瘍治療ガイドライン
がん情報サービスによる脳腫瘍治療の包括的説明

脳浮腫の病態とメカニズムに関する詳細解説