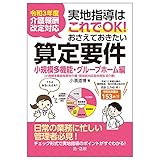在宅中心静脈栄養法加算
算定要件と2024改定のポイント
在宅医療のニーズが高まる中、中心静脈栄養(TPN)を在宅で実施する患者への薬学的管理は、感染対策や事故防止の観点から極めて重要です。在宅中心静脈栄養法加算は、こうした高度な管理が必要な患者に対して、薬剤師が専門性を発揮して安全管理を行った場合の手間を評価するものです。
まず、基本的な算定要件を確認しましょう。この加算は、在宅で中心静脈栄養を行っている患者に対して、患家を訪問し、以下の点を確認・指導した場合に、1回につき150点を算定できます。
- 投与及び保管状況の確認
- 配合変化の有無の確認
- 処方医や他職種への情報提供
ここで特に注意が必要なのが、「患家を訪問し」という部分です。昨今普及している「情報通信機器を用いた服薬指導(オンライン服薬指導)」においては、この加算は算定できません。これは、TPNの管理において、輸液バッグの保管場所の衛生状態、輸液ラインの屈曲や閉塞のリスク、実際の投与手技の環境など、画面越しでは把握しきれない「現場のリスク」を肌で感じ取り、是正することが求められているためです。
2024年度の改定では、大きな変更点がありました。以前は医療保険の「在宅患者訪問薬剤管理指導料」などの加算として位置づけられていましたが、今回の改定により、介護保険の「居宅療養管理指導費」を算定している場合でも、同様の評価(150単位)が算定可能となりました。
これは、要介護高齢者の在宅療養が増加し、介護保険下でも医療依存度の高いTPN管理が必要なケースが増えている実態に即したものです。ただし、算定ルールは医療保険と同様に厳格であり、単に訪問するだけでなく、薬学的管理の質が問われます。例えば、訪問時に輸液の残量を確認し、次回配送の調整を行うといった事務的な作業だけでは要件を満たしません。「配合変化の確認」や「保管状況の指導」といった、薬剤師ならではの視点での介入記録が必須となります。
居宅療養管理指導における在宅中心静脈栄養法加算の解説(カイポケ)
また、この加算は「麻薬」に関する加算とも併算定が可能です。末期がん患者などで、TPNと同時に持続的な麻薬投与が行われている場合、「在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算」も同時に算定できるため、複雑な病態管理を行う薬局にとっては重要な収益源かつ評価指標となります。
無菌製剤処理加算との併算定
在宅中心静脈栄養法加算を算定する際、セットで考えるべきなのが「無菌製剤処理加算」との併算定です。多くの薬局では、クリーンベンチや安全キャビネットを備え、TPN製剤の混注業務を行っているかと思いますが、この二つの加算の関係性を正しく理解していないと、算定漏れや過誤請求の原因となります。
結論から言えば、在宅中心静脈栄養法加算と無菌製剤処理加算は併算定が可能です。これは、それぞれの加算が評価しているポイントが異なるためです。
- 在宅中心静脈栄養法加算(150点): 患家を訪問し、現場での管理・指導・環境確認を行う「対人業務」への評価。
- 無菌製剤処理加算(69点〜): 薬局内で無菌的に薬剤を混合調製する「対物業務(技術)」への評価。
つまり、薬局で無菌調製を行い、その薬剤を持って患者宅を訪問し、適切な管理指導を行えば、両方の点数を算定することができます。無菌製剤処理加算の点数は、対象となる薬剤によって異なります。
注意すべきは、「同一日の使用のために製剤した場合」の取り扱いです。例えば、同じ日に使用するためにTPN輸液と抗がん剤の両方を無菌調製した場合、両方の点数を単純に足すことはできません。原則として、主たるもの(点数が高い方)のみを算定します。しかし、これらはあくまで「調製技術」に対する評価であり、在宅中心静脈栄養法加算という「管理指導」への評価とは別枠であるため、混同しないようにしましょう。
さらに、無菌調製を外部に委託している場合や、病院から処方箋を受けて調剤のみを行う場合の連携も重要です。自局で無菌調製を行わず、他局や病院で調製された製剤を受け取って訪問する場合、当然ながら自局では無菌製剤処理加算は取れませんが、在宅中心静脈栄養法加算は「管理指導」を行えば算定可能です。この場合、調製を行った施設と連携し、どのような配合変化のリスクがあるか、調製から投与までの安定性データなどを共有しておくことが、質の高い指導につながります。
輸液セットと注入ポンプ加算の注意点
ここからは、意外と見落としがちな「医療材料」や「機器」に関連する加算の落とし穴について解説します。特に「在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算」(C160)と「注入ポンプ加算」(C161)は、請求時にミスが多発するポイントです。
最も注意すべきなのが、輸液セットの「7組目ルール」です。
通常、在宅でTPNを行うために必要な輸液セット(バッグ、ライン、ヒューバー針など)を交付した場合、月単位で「在宅中心静脈栄養法用輸液セット加算(2000点)」を算定します。しかし、この加算が適用されるのは、1月に6組までの場合です。
もし、患者の状態により頻回な交換が必要で、1月に7組以上の輸液セットを使用・交付した場合はどうなるでしょうか?この場合、7組目以降は「加算」ではなく、「特定保険医療材料」として請求しなければなりません。
- 月1〜6組: まとめて「輸液セット加算(2000点)」として算定。
- 月7組目以降: 個別の「特定保険医療材料(002 在宅中心静脈栄養用輸液セット)」として、実数分を算定。
この切り替えをレセプトコンピュータの設定任せにしていると、自動計算されずに請求漏れが発生したり、逆に過剰に算定して返戻になったりするケースがあります。特に、カテーテルトラブルで予期せぬ交換が発生した月などは要注意です。
在宅療養指導管理料算定時の輸液セット加算の注意点(日の出クリニック)
また、「注入ポンプ加算」についても理解が必要です。これは、在宅で注入ポンプを使用する場合に、2月に2回(つまり月1回程度)、1250点を算定できるものです。ここで重要なのは、「ポンプを実際に使用しているか」という実態確認です。ポンプをレンタルしていても、患者の状態変化により一時的に自然滴下(クランプ調整)に変更している期間などは、厳密には算定要件を満たさない可能性があります。
さらに、この注入ポンプ加算には、ポンプのレンタル料が含まれていると考えられています。そのため、別途患者にレンタル料を請求することはできません。薬局側がポンプを購入またはリースして患者に貸与するコストと、この加算点数のバランスを経営的に考慮する必要があります。高機能なポンプは高額ですが、アラート機能が充実しており患者の安全につながるため、コストだけで選定するのは危険です。
注入ポンプ加算とレンタル料の関係に関するQ&A(しろぼんねっと)
このように、モノ(輸液セット・ポンプ)と技術(指導・管理)の点数が複雑に絡み合っているのがこの分野の特徴です。「加算」という名前だけで判断せず、その裏にある「数量制限」や「提供形態」まで把握しておくことが、正確な請求への第一歩です。
薬剤師視点の配合変化とリスク管理
検索上位の記事では「算定要件」や「点数」の話が中心ですが、現場の薬剤師が最も頭を悩ませ、かつ腕の見せ所となるのが「配合変化(インコンパチビリティ)」の回避とリスク管理です。在宅中心静脈栄養法加算の要件にも「配合変化の有無の確認」が明記されていますが、具体的に何を見るべきでしょうか?
独自視点として、「在宅特有の環境要因による配合変化リスク」を掘り下げます。
病院内とは異なり、在宅では温度管理や光の曝露状況が一定ではありません。
1. カルシウムとリンの結晶化リスク
TPN製剤において最も警戒すべき配合変化の一つが、カルシウム製剤とリン製剤の反応による難溶性塩(リン酸カルシウム)の析出です。これは輸液ラインの閉塞や、最悪の場合は肺塞栓を引き起こす致死的なリスクがあります。
この反応は、pHが高いほど、また温度が高いほど促進されます。在宅環境では、夏場に冷房が切れた部屋で輸液が保管されたり、冬場に暖房器具の近くに置かれたりすることで、想定外の温度上昇が起こり得ます。薬剤師は、処方監査の段階でCa/P比を確認するだけでなく、「ご自宅のどこに輸液を置いているか」「直射日光や温風が当たっていないか」を訪問時に必ず目視確認する必要があります。
2. ビタミンの光分解と着色
マルチビタミン製剤が含まれるTPN輸液は、光に対して不安定です。特にビタミンB群やC、Kは光分解されやすく、遮光カバーの使用が必須です。しかし、在宅では「残量が見にくいから」という理由で、患者や家族が勝手に遮光カバーを外してしまうケースが散見されます。
訪問時には、単に「遮光してください」と伝えるだけでなく、「なぜ遮光が必要なのか(薬の効果がなくなる、分解産物が体に悪影響を与える可能性がある)」を具体的に説明し、カバーが正しく装着されているかを確認することが、プロフェッショナルな管理です。
TPN輸液の調製方法と配合変化のチェックポイント(PEGドクターズネットワーク)
3. カテーテル関連血流感染症(CRBSI)の予兆発見
薬剤師は医師や看護師ではありませんが、訪問時に「輸液ラインの接続部」や「刺入部周辺」の異常に気付くことができます。
例えば、「輸液ライン内に浮遊物や混濁がないか」を確認することは、配合変化のチェックであると同時に、細菌塊や真菌塊の発見にもつながります。また、患者が「最近、点滴をつなぐと寒気がする」と訴えた場合、それはCRBSIの初期症状(悪寒戦慄)かもしれません。こうした患者の何気ない訴えを「副作用かな?」で済ませず、即座に主治医や訪問看護師にフィードバックできるかどうかが、在宅チーム医療における薬剤師の価値を決定づけます。
薬歴記載の必須事項と具体例
最後に、在宅中心静脈栄養法加算を算定する上で避けて通れないのが「薬歴(薬剤服用歴)への記載」です。厚生局の個別指導においても、この記載不備が指摘事項として挙がることが非常に多くなっています。単に「TPN指導実施」と書くだけでは不十分です。
要件を満たすために、以下の3点は必ず盛り込む必要があります。
- 投与および保管の状況
- 配合変化の有無の確認
- 他職種への情報提供内容
これらを網羅した、より具体的な薬歴記載のテンプレート(良い例)を紹介します。
【良い薬歴記載例】
- S(Subjective): 「点滴の管が少し邪魔で寝返りがしにくい。熱はない。」
- O(Objective):
- バイタル:BP 128/78, P 72, SpO2 98%。刺入部の発赤・腫脹なし。
- 保管状況: 冷暗所(北側の廊下収納)にて保管確認。直射日光なし。
- 投与状況: ポンプ設定流量 40mL/h、閉塞アラーム履歴なし。ルートの屈曲なし。
- 配合変化: 輸液バッグ内およびライン内に結晶析出、混濁、変色なし。側管からの他剤混注なしを確認。
- A(Assessment): 保管・投与環境は良好。配合変化の兆候も見られない。患者の寝返り時のルートトラブル懸念に対し、チューブの固定位置の工夫が必要と判断。
- P(Plan):
- 指導: ループを作ってゆとりを持たせた固定方法を家族に実演指導。就寝時のポンプ配置位置をベッド足元から頭側へ変更提案。
- 情報提供: 訪問看護師へ、寝返り時のルート牽引リスクについて共有し、次回訪問時の刺入部固定確認を依頼(FAXにて送信済)。
【悪い記載例】
- TPNの指導を行った。
- 問題なし。
- 医師へ報告した。
このように、具体的な確認内容が欠落していると、算定要件である「配合変化の有無」や「保管状況」を確認した証拠にならず、返戻の対象となり得ます。特に「何を見て問題なしと判断したのか」(例:結晶析出なし、混濁なし)を明記することが、自分自身の身を守ることにもつながります。AIによる音声入力なども活用し、効率的かつ漏れのない記録作成を心がけましょう。