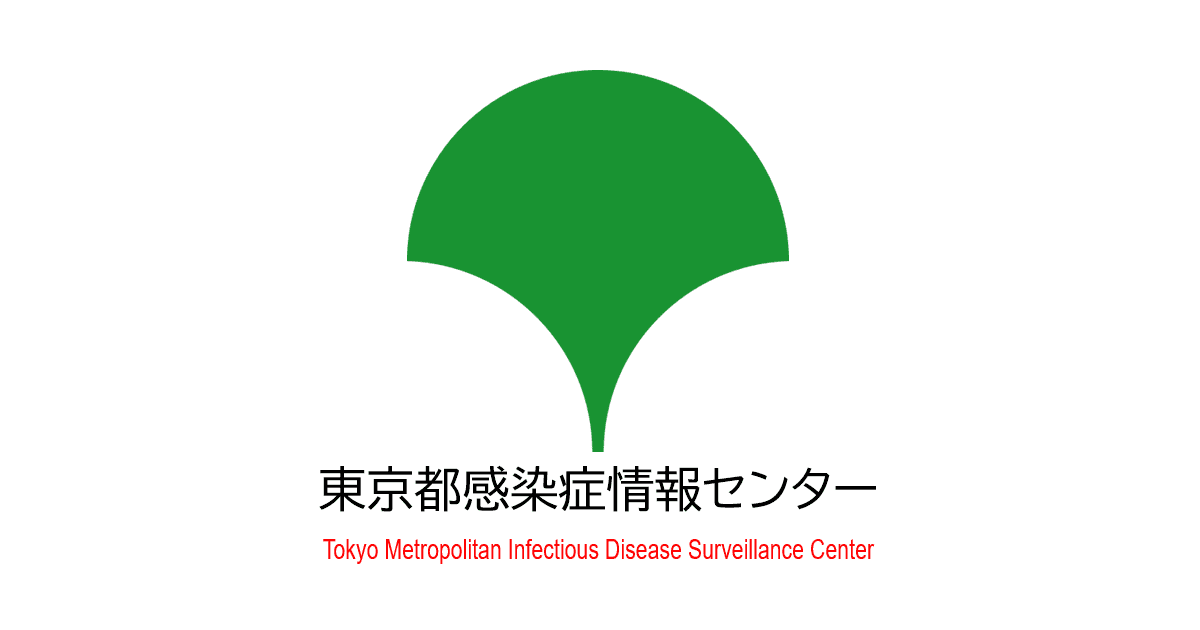カルバペネム耐性腸内細菌科細菌の感染対策と治療
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌の基本的特徴と分類
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌(CRE:Carbapenem-resistant Enterobacteriaceae)は、最後の切り札的抗菌薬であるイミペネムやメロペネムなどのカルバペネム系抗菌薬に対し耐性を獲得した腸内細菌科細菌の総称です。
CREの定義は、メロペネムなどのカルバペネム系薬剤及び広域β-ラクタム剤に対して耐性を示す腸内細菌科細菌による感染症とされています。具体的には以下の基準で判定されます。
主な対象菌種
CREは大きく2つのカテゴリに分類されます。
- カルバペネマーゼ産生腸内細菌科細菌(CPE):カルバペネマーゼという酵素を産生してカルバペネムを分解する
- 非カルバペネマーゼ産生CRE(non-CP-CRE):ESBLやAmpCなどの広域β-ラクタマーゼ産生に加えて外膜蛋白の透過性低下により耐性化
特に注目すべきは、日本国内ではIMP型カルバペネマーゼが主流である一方、海外ではKPC型、NDM型、OXA-48型が多いという地域差があることです。
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌の感染経路と病院感染対策
CREの感染経路は主に接触感染であり、医療現場での感染拡大を防ぐためには厳重な感染対策が必要です。
主要な感染経路
- 接触感染:汚染された医療器具や医療従事者の手を介した感染
- 飛沫感染:呼吸器感染症をきたした場合の伝播
- 腸管内定着:一度定着すると長期間保菌状態が続く
感染対策の実際
病室管理においては、個室隔離が基本となります。
- 個室を用意し、入口のカーテンを除去
- PPE(個人防護具)ホルダーの設置
- 接触感染予防策ポスターの掲示
医療従事者の個人防護具着用
- 手袋の着用(患者接触前)
- ガウンまたはエプロンの着用
- 手指衛生の徹底(アルコール系手指消毒剤の使用)
興味深いことに、UV-C紫外線照射システムを用いた病室内の紫外線殺菌消毒の有効性についても研究が進んでおり、従来の清拭消毒と併用することで、より効果的な環境除菌が可能となっています。
保菌状態の判定と解除基準
一旦体内に定着したCREは体内から完全に消失することはなく、潜伏状態(保菌状態)が続くと考えられています。しかし、以下の条件を満たした場合には伝播源となる可能性が低くなったと判断し、標準予防策での対応が可能となります。
- 1週間以上の間隔で実施した培養検査で3回連続してCREが検出されない
- 特別な選択培地による検査が必要
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌に対する治療薬選択と併用療法
CRE感染症の治療において最も重要なのは、カルバペネム耐性を引き起こすβ-ラクタマーゼの種類を特定することです。これにより適切な治療選択肢が決定されます。
Ambler分類による治療選択
カルバペネマーゼはAmbler分類に基づいてclass A、B、Dに分類され、各クラスに応じた治療選択肢があります。
Class A(KPC型)
Class D(OXA-48-like)
- セフタジジム/アビバクタム
- セフィデロコル
Class B(メタロ-β-ラクタマーゼ:MBL)
- セフタジジム/アビバクタム+アズトレオナムの併用療法
- セフィデロコル
従来の治療薬剤
高度耐性のCPEに対して用いられる主な治療薬は以下の通りです。
併用療法の重要性
単剤治療よりも2〜3種類の薬剤を併用することで、治療成績が向上することが知られています。興味深いことに、カルバペネム系薬剤も薬剤感受性成績が高度耐性(MIC>8 μg/mL)でなければ、他の薬剤と併用することで効果が期待できます。
日本の特殊事情
本邦では、MBL産生腸内細菌科細菌の大部分をIMP型が占め、海外でKPCやNDMが主であることとは大きく異なる疫学的特徴があります。このため、治療戦略も欧米とは異なるアプローチが必要となる場合があります。
厚生労働省のIASRによる最新の治療指針では、カルバペネマーゼの種類に応じた標的治療の重要性が強調されており、適切な診断と治療選択が患者予後の改善につながることが示されています。
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌の検出方法と診断技術
CREの正確な検出と診断は、適切な治療と感染対策の基盤となります。特に「ステルス型」と呼ばれるIMP-6産生菌株のように、従来の検査では見逃されやすい菌株の存在が問題となっています。
検出技術の進歩
現在の検出技術には以下のような特徴があります。
- MicroScan WalkAway装置:自動化された感受性試験装置による検出能力の評価が進んでいます
- ESBL/MBL選択培地:カルバペネム耐性菌の選択的検出に有用
- 全ゲノム解析(WGS):遺伝子レベルでの詳細な解析が可能
IMP-6型カルバペネマーゼの特殊性
日本で特に注目されているのがIMP-6型カルバペネマーゼ産生菌です。この菌株には以下の特徴があります。
診断のポイント
便培養検体での検査では、初回提出検体と前回検査から1か月以上経過した検体について、ESBL/MBL選択培地での検査が実施されます。特定の検査を希望する場合は、オーダー画面で「CRE」とフリー入力することが推奨されています。
新規検出患者への対応
CREが新規に検出された患者に対しては、以下のサーベイランス体制が整備されています。
- 2014年1月から2015年12月の2年間のデータでは、新規検出患者の動向が詳細に分析
- 病院内でのアウトブレイク対応プロトコルの整備
- 感染症法に基づく届出の徹底
これらの検査技術の進歩により、早期発見と適切な対応が可能となり、院内感染の拡大防止に大きく貢献しています。
カルバペネム耐性腸内細菌科細菌の新規治療戦略と研究動向
CRE感染症に対する治療法の開発は急速に進歩しており、従来の抗菌薬に加えて革新的なアプローチが研究されています。
新規治療法の開発
最新の研究では、オートインデューサーアナログ(AIA)-1という化合物を用いた新しい治療アプローチが注目されています。この研究では。
分子疫学的アプローチ
環境中でのカルバペネマーゼ遺伝子の分布についての研究も進んでいます。興味深い知見として。
- ヒト、動物、食品、環境からのカルバペネマーゼ遺伝子の検出
- 腸内細菌目は7つの科、60の属、250種以上を含む大きな分類群
- 水平遺伝子伝達による耐性遺伝子の拡散メカニズムの解明
国際的な研究動向
世界的には以下のような治療薬の開発が進んでいます。
- 新規β-ラクタマーゼ阻害薬配合剤:より強力な阻害効果を持つ薬剤
- 新世代テトラサイクリン系薬:従来のテトラサイクリンより優れた特性
- シデロフォア構造を有する薬剤:鉄取り込みシステムを利用した新しい作用機序
地域差を考慮した治療戦略
日本独特の疫学的特徴を踏まえた治療戦略も重要です。
- IMP型カルバペネマーゼが主流である日本の状況
- 海外のKPC型、NDM型とは異なる耐性パターン
- 地域の抗菌薬使用パターンとの関連性の分析
将来展望
CRE感染症の治療において、今後期待される発展として。
- 個別化医療に基づく治療選択
- 迅速診断技術と治療選択の連動
- 予防的アプローチの強化
- 新規作用機序を持つ抗菌薬の臨床応用
これらの研究成果により、CRE感染症の予後改善と感染拡大の防止が期待されており、医療従事者にとって重要な治療選択肢の拡大につながっています。
各研究機関での取り組みにより、従来の抗菌薬治療の限界を突破する新しい治療パラダイムの確立が進んでおり、臨床現場での実用化が待たれています。
CREに対する治療戦略参考情報(最新の治療指針について詳細な解説)
東京都の感染症対策情報(CRE感染症の基礎知識と対策)