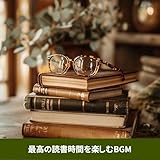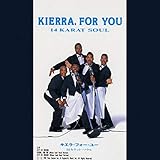ビーフリードの投与時間と注意点
ビーフリードの投与時間と投与速度の基本【添付文書より】
ビーフリード輸液は、経口摂取が不十分な患者さんに対して水分、電解質、アミノ酸、ビタミンB1、糖質を補給するための末梢静脈栄養輸液です 。アミノ酸と糖質を同時に投与することで、アミノ酸の有効利用が期待できます 。この輸液は使用時に隔壁を開通し、上室液(アミノ酸、電解質、ビタミンB1)と下室液(ブドウ糖)を混合して使用します 。
添付文書によると、ビーフリードの基本的な投与方法は以下の通りです 。
- 用法・用量: 通常、成人には1回500mLを末梢静脈内に点滴静注します 。
- 投与速度: 通常、成人500mLあたり120分(約2時間)を基準とします 。
なぜこの投与速度が基準とされているのでしょうか。その理由は、ビーフリードに含まれる成分と浸透圧にあります。急速に投与すると、ブドウ糖による高血糖や、それに伴う浸透圧利尿、さらにはアミノ酸による悪心・嘔吐などの副作用を引き起こす可能性があります 。また、投与終了後の反動で低血糖を起こす危険性も指摘されています 。
参考)医療用医薬品/医療機器|よくある質問|【公式】大塚製薬工場 …
この基準速度は、ブドウ糖の最大投与速度(0.5g/kg/時)とアミノ酸の最大投与速度(0.2g/kg/時)を超えないように設定されており、臨床試験で安全性が確認された速度です 。安全な投与を徹底するためにも、この「500mLあたり120分」という基準を必ず守ることが重要です。
また、長時間の投与は細菌汚染のリスクを高めることが知られています 。特に、薬剤を混注した場合、投与時間が長引くと細菌が増殖し、菌血症を引き起こす危険性が増大します 。そのため、添付文書の基準時間を守り、可能な限り単剤で、清潔な操作を心掛けることが推奨されています 。ある報告では、投与時間は6〜8時間を限度とすべきであると提言されています 。
参考)https://chuo.kcho.jp/app/wp-content/uploads/2022/03/NStimes27.pdf
ビーフリード投与における血管痛や静脈炎のリスクと対策
ビーフリードの投与で最も頻繁に遭遇するトラブルの一つが、血管痛や静脈炎です 。多くの看護師が、患者さんからの「腕がピリピリする」「痛い」といった訴えを経験したことがあるでしょう 。この血管痛の主な原因は、ビーフリードの高い浸透圧にあります 。
血液の浸透圧比が約1であるのに対し、ビーフリードの浸透圧比は約2.5と、血液よりもかなり高くなっています 。浸透圧の高い液体が血管内に入ると、その圧力の差によって血管の内側の壁(血管内皮細胞)から水分が奪われ、細胞が傷つけられます 。これが刺激となり、痛みや炎症(静脈炎)を引き起こすのです 。
youtube
💉 血管痛・静脈炎への具体的な対策
- 穿刺部位の選択: なるべく太く、血流の豊富な血管を選びましょう 。細い血管や、関節付近など屈曲しやすい部位は避けるのが賢明です。
- 投与速度の調整: 添付文書の基準(500mL/120分)を守り、それでも痛みを訴える場合は、医師に報告の上でさらにゆっくりと投与速度を落とすことを検討します 。
- 温める: 穿刺部位や腕全体を温めることで血管が拡張し、血流が促進されます。これにより、輸液が血液と速やかに混ざり合い、血管壁への刺激が緩和されます 。蒸しタオルやホットパックの利用が効果的です。
- 希釈して投与: 浸透圧の低い輸液(生理食塩水など)と同時に別のルートから投与するか、Y字管を用いて希釈しながら投与する方法もありますが、医師の指示が必要です 。
- こまめな観察: 投与中は定期的に穿刺部位の発赤、腫脹、硬結、熱感、そして痛みの有無を観察することが極めて重要です 。血管外漏出の早期発見にも繋がります 。
血管痛の訴えがあった場合、まずは我慢させずに点滴を一旦止めるか、速度を落とすなどの対応が必要です 。逆血を確認し、血管外漏出でないことを確認した上で、上記の対策を講じましょう 。
参考)https://kango-oshigoto.jp/hatenurse/article/1416/
ビーフリードを高齢者へ投与する際の投与時間と注意点
高齢者への輸液療法は、成人と同様の考え方では思わぬリスクを招くことがあります。ビーフリードの添付文書にも「高齢者、重篤な患者には更に緩徐に注入する」と明記されている通り、特に慎重な投与が求められます 。
高齢者は、加齢に伴い様々な生理機能が低下しています。特に心機能や腎機能の低下は、輸液管理に大きく影響します 。
参考)第10回 一歩進んだ輸液の考え方 – 総合内科流 一歩上を行…
👴 高齢者への投与で特に注意すべき3つのポイント
- 心機能の低下と循環血液量: 高齢者は心臓のポンプ機能が低下しているため、急激に輸液を投与すると心臓に負担がかかり、心不全や肺水腫を引き起こす危険性があります。投与速度を通常よりも遅く設定し、循環器系の変動に注意深く対応する必要があります。
- 腎機能の低下と水分・電解質バランス: 腎臓の機能が低下していると、水分やナトリウムなどの電解質をうまく排泄できなくなります 。ビーフリードには電解質も含まれているため、過剰投与になると高ナトリウム血症や高カリウム血症、水分過剰(浮腫)などをきたしやすくなります。カリウムの必要量も成人より少ない場合があります 。
- 耐糖能の低下と高血糖: 高齢者はインスリンの分泌能力や感受性が低下していることが多く、糖質を含む輸液によって容易に高血糖をきたす可能性があります 。高血糖は感染症のリスクを高めるだけでなく、意識障害につながることもあるため、定期的な血糖チェックが欠かせません 。
これらのリスクを回避するため、高齢者へのビーフリード投与では、以下の観察項目(アセスメント)が重要になります。
📈 高齢者への投与中の観察項目
- バイタルサイン: 血圧、脈拍、呼吸数の変動に注意。特に頻脈や呼吸困難は心不全の兆候かもしれません。
- 水分出納バランス: IN/OUTバランスを正確に把握し、尿量の減少や浮腫の出現に注意します。体重の変動も重要な指標です。
- 血糖値: 定期的に血糖値を測定し、高血糖や低血糖の兆候がないか確認します 。
- 一般状態: 倦怠感、口渇、意識レベルの変化など、患者さんの自覚症状や様子の変化を見逃さないようにします。
投与時間は患者さんの状態に合わせて個別に設定する必要があります。一律に「120分」と考えるのではなく、常に患者さんを観察し、異常の早期発見に努める姿勢が安全な投与に繋がります 。
参考)https://kango-oshigoto.jp/hatenurse/article/1692/
以下の参考リンクは、高齢者の輸液療法に関する考え方を学ぶ上で非常に有用です。
ビーフリードの投与時間を守るための実践的な滴下計算方法
ビーフリードの投与時間を正確に守るためには、1分間あたりの滴下数を計算し、クレンメを調整する必要があります。この計算は看護業務の基本ですが、焦っている時ほどうっかり間違えやすいものです。ここで改めて計算方法とポイントをおさらいしましょう。
滴下数の計算式は以下の通りです。
1分間の滴下数 = (輸液総量[mL] × 1mLあたりの滴下数[滴]) ÷ 投与時間[分]
計算の鍵となるのが「1mLあたりの滴下数」です。これは使用する輸液セットによって異なります。
- 成人用輸液セット: 一般的に 20滴/mL です。
- 小児用・精密輸液セット: 一般的に 60滴/mL です。
では、ビーフリード500mLを添付文書の基準通り120分で投与する場合を例に計算してみましょう。
【例題1】成人用ルート(20滴/mL)を使用する場合
- 計算式: (500mL × 20滴) ÷ 120分
- 計算結果: 10000 ÷ 120 ≒ 83.3滴/分
- 調整の目安: 60秒で約83滴、つまり3秒で約4滴となります。
【例題2】小児用ルート(60滴/mL)を使用する場合
- 計算式: (500mL × 60滴) ÷ 120分
- 計算結果: 30000 ÷ 120 = 250滴/分
- 調整の目安: 成人用ルートの3倍の速度となり、目視での調整は非常に困難です。このような場合は輸液ポンプの使用が原則となります。
下の表は、ビーフリード500mLを異なる時間で投与する場合の1分間あたりの滴下数の早見表です。臨床現場でご活用ください。
| 投与時間 | 成人用 (20滴/mL) | 小児用 (60滴/mL) |
|---|---|---|
| 120分 (2時間) | 約83滴/分 | 250滴/分 |
| 180分 (3時間) | 約56滴/分 | 167滴/分 |
| 240分 (4時間) | 約42滴/分 | 125滴/分 |
正確な投与のためには、滴下数を合わせるだけでなく、定期的に残量を確認し、予定通りに投与が進んでいるかを確認する習慣が大切です。
ビーフリード投与中止の判断基準と中止後のアセスメント
ビーフリードの安全な投与には、開始時の設定だけでなく、「いつ中断・中止すべきか」という判断も同様に重要です。このセクションでは、検索上位にはあまり見られない「投与中止」の視点から、臨床判断に役立つ情報を提供します。
投与を直ちに中止し、医師に緊急報告が必要な兆候として、アナフィラキシーショックが挙げられます。頻度は不明ながらも重大な副作用として報告されており、以下の初期症状を見逃してはいけません。
🚨 アナフィラキシーの初期症状
これらの症状が一つでも現れた場合は、直ちに投与を中止し、バイタルサインの確認と気道確保、医師への迅速な報告と救急カートの準備など、緊急時対応を開始します。
そこまで緊急性は高くないものの、投与の継続を慎重に検討、または医師に報告・相談すべき状況もあります。
⚠️ 投与継続を検討・相談すべき状況
- 強い血管痛や広範囲の発赤: 温罨法や速度調整を行っても改善しない、または悪化する強い血管痛は、重度の静脈炎や血栓形成のリスクを示唆します 。我慢させずに医師に報告し、ルートの変更や薬剤の変更を検討します。
- 血管外漏出の疑い: 穿刺部の著明な腫脹、冷感、痛みの増強、点滴の滴下不良が見られた場合は血管外漏出が強く疑われます 。直ちに投与を中止し、針を抜去します。その後、患部を挙上し、薬剤の種類に応じて冷罨法または温罨法を行いますが、ビーフリードのような高浸透圧の薬剤では、炎症を広げないためにまず冷やすことが推奨される場合があります。必ず施設のプロトコルを確認し、医師の指示を仰いでください。
- 急激なバイタルサインや血糖値の変動: 投与開始後に明らかな血圧の変動、頻脈、呼吸状態の変化や、著しい高血糖(例: 300mg/dL以上)または低血糖症状(冷や汗、動悸など)が出現した場合、投与速度が患者さんの状態に合っていない可能性があります 。投与を中止または最スローで継続し、速やかに医師に報告が必要です。
- 悪心・嘔吐の出現: アミノ酸の急速な投与により、悪心・嘔吐が出現することがあります 。症状が軽度であれば投与速度を落とすことで改善する場合もありますが、持続する場合は消化器系の異常や代謝異常も考慮し、医師に報告します。
投与を中止した後も、看護師の役割は終わりません。中止に至った原因をアセスメントし、患者さんの状態変化を継続して観察する必要があります。バイタルサインの推移、中止後の症状の変化(軽快または悪化)、穿刺部の状態などを正確に記録し、その後の治療方針決定のための重要な情報としてチームで共有しましょう。