ACE阻害薬の強さ比較
ACE阻害薬の強さを比較する降圧効果と心保護効果の一覧
ACE阻害薬(アンジオテンシン変換酵素阻害薬)は、高血圧治療の第一選択薬の一つとして広く用いられています。その「強さ」を比較する際には、単に血圧を下げる「降圧効果」だけでなく、心臓や腎臓といった重要な臓器を保護する「臓器保護効果」も総合的に評価することが極めて重要です。
降圧効果の比較
ACE阻害薬の降圧効果は、アンジオテンシンIIという強力な血管収縮物質の産生を抑制することによってもたらされます。しかし、薬剤の種類によってその効果の強さや持続時間には違いがあります。
一般的に、1日1回の投与で安定した降圧効果が得られる薬剤が主流ですが、効果のピークや半減期はそれぞれ異なります。例えば、長時間作用型の薬剤は、血圧の日内変動を安定させ、早朝高血圧のリスクを低減させるのに有用です。
以下に、代表的なACE阻害薬の降圧効果の力価(目安)を比較した表を示します。ただし、これはあくまで一般的な目安であり、個々の患者さんの病態や遺伝的背景によって効果は変動します。
| 薬剤名(一般名) | 力価(相対的な強さ) | 特徴 |
|---|---|---|
| ペリンドプリル | 高 | 組織移行性が高く、長時間作用する。 |
| イミダプリル | 中〜高 | 降圧効果がマイルドで、副作用が少ないとされる。 |
| エナラプリル | 中 | 古くから使用され、エビデンスが豊富。 |
| カプトプリル | 低(短時間型) | 1日2〜3回の服用が必要。効果発現が速い。 |
心保護効果と腎保護効果
ACE阻害薬の真価は、降圧効果だけにとどまりません。心臓や腎臓に対して優れた保護作用を発揮することが、数多くの大規模臨床試験で証明されています。
- 心保護効果 ❤️: 心筋梗塞後の心不全進展の抑制、心肥大の改善、心血管イベントのリスク低下などが報告されています。これは、アンジオテンシンIIによる心筋のリモデリング(線維化など)を抑制する作用が関与しています。特に、ペリンドプリルは、EUROPA試験において、安定冠動脈疾患患者の心血管イベントを有意に抑制することが示されました。(参考文献: The European trial on reduction of cardiac events with perindopril in stable coronary artery disease (EUROPA) investigators. Efficacy of perindopril in reduction of cardiovascular events among patients with stable coronary artery disease: randomised, double-blind, placebo-controlled, multicentre trial (the EUROPA study). Lancet. 2003 Sep 6;362(9386):782-8.)
- 腎保護効果 🛡️: 糖尿病性腎症や慢性腎臓病(CKD)の進行を抑制する効果があります。これは、腎臓の糸球体内圧を低下させ、タンパク尿を減少させる作用によるものです。大規模臨床試験であるREIN試験では、ACE阻害薬がタンパク尿を有するCKD患者の腎不全への進行を遅らせることが示されています。
これらの臓器保護効果は、必ずしも降圧効果の強さと比例するわけではありません。薬剤の組織への移行性や、ブラジキニン分解抑制作用の強さなども関与すると考えられており、薬剤選択において重要な視点となります。
参考情報:ACE阻害薬の臓器保護効果に関する詳細な解説
日本循環器学会 高血圧治療ガイドライン
ACE阻害薬の種類とそれぞれの作用機序の特徴
ACE阻害薬は、体内でアンジオテンシンIからアンジオテンシンIIへの変換を担う「アンジオテンシン変換酵素(ACE)」を阻害することで効果を発揮します。しかし、一口にACE阻害薬と言っても、その化学構造や体内動態によっていくつかの種類に分類され、それぞれに特徴があります。
プロドラッグと活性代謝物
多くのACE阻害薬は「プロドラッグ」と呼ばれる形態で投与されます。プロドラッグとは、そのままでは薬理活性を持たず、体内で代謝されることによって初めて活性型の物質に変化する薬剤のことです。
- プロドラッグの利点: 消化管からの吸収率を高めたり、作用の持続時間を長くしたりすることができます。例えば、エナラプリルは経口投与後、肝臓で代謝されて活性体であるエナラプリラートに変換されます。
- 活性代謝物の特徴: カプトプリルやリシノプリルは、プロドラッグではなく、それ自体が活性を持つ薬剤です。これらの薬剤は、肝機能が低下している患者さんでも代謝の影響を受けにくいため、使いやすい場合があります。
作用機序の共通点と相違点
全てのACE阻害薬に共通する基本的な作用機序は、レニン・アンジオテンシン(RAA)系の抑制です。
レニン(腎臓) → アンジオテンシノーゲン(肝臓) → アンジオテンシンI → (ACE) → アンジオテンシンII(強力な血管収縮作用)
ACE阻害薬はこの経路の(ACE)をブロックします。しかし、ACEは「キニナーゼII」という別名も持っており、血管拡張作用を持つ「ブラジキニン」という物質を分解する酵素でもあります。
ブラジキニン(血管拡張作用) → (キニナーゼII) → 不活性物質
つまり、ACE阻害薬は、以下の2つの作用を同時に発揮します。
- アンジオテンシンIIの産生抑制: 血管を収縮させ、血圧を上昇させる物質を減らす。
- ブラジキニンの分解抑制: 血管を拡張させ、血圧を下降させる物質を増やす。
このブラジキニンの増加が、降圧効果を補助すると同時に、後述する「空咳」という副作用の主な原因にもなっています。薬剤によって、このブラジキニンへの影響度が若干異なるとも言われており、それが副作用の発現頻度の違いにつながっている可能性が考えられます。
各薬剤の化学構造と特徴
ACE阻害薬は、その化学構造中に持つ亜鉛結合基によって、スルフィドリル基(-SH基)、カルボキシル基(-COOH基)、ホスフィニル基(-POOH基)を持つものに大別されます。
| 分類 | 代表的な薬剤 | 特徴 |
|---|---|---|
| スルフィドリル基含有 | カプトプリル | 最初に開発されたACE阻害薬。短時間作用型。味覚異常や皮疹などの副作用が比較的多いとされる。 |
| カルボキシル基含有 | エナラプリル、イミダプリル、ペリンドプリル、リシノプリルなど | 現在主流のグループ。長時間作用型のプロドラッグが多い。 |
| ホスフィニル基含有 | ホシノプリル | 肝臓と腎臓の両方から排泄されるという特徴を持つ。 |
これらの化学構造の違いが、体内での吸収、分布、代謝、排泄(体内動態)に影響を与え、結果として作用時間や副作用のプロファイルに違いを生み出しています。
ACE阻害薬で注意すべき副作用「空咳」とブラジキニンの関係
ACE阻害薬を服用する上で最も頻度が高く、患者さんの服薬継続(アドヒアランス)を妨げる原因となるのが「空咳(からぜき)」です。この副作用は、喘息の既往がないにもかかわらず、痰を伴わない乾いた咳が続くのが特徴で、特に夜間や早朝に悪化する傾向があります。
なぜ空咳が起こるのか?
空咳の主な原因は、ACE阻害薬の作用機序そのものにあります。前述の通り、ACE阻害薬はアンジオテンシン変換酵素(ACE)を阻害しますが、このACEは「キニナーゼII」として、気管支などに存在する知覚神経刺激物質「ブラジキニン」を分解する役割も担っています。
ACE阻害薬によってキニナーゼIIの働きがブロックされると、ブラジキニンが分解されずに気道に蓄積します。蓄積したブラジキニンが気道のC線維(知覚神経)を刺激し、咳反射を引き起こすと考えられています。
- ブラジキニンの蓄積: ACE阻害により分解が抑制される。
- 知覚神経の刺激: 気道にある咳受容体が過敏になる。
- 咳反射の亢進: 乾いたしつこい咳が誘発される。
この副作用は用量依存的ではなく、少量の服用でも起こり得ます。また、人種差があり、日本人を含む東アジア人では発現頻度が高いことが報告されています。
空咳の発現時期と対処法
空咳は、ACE阻害薬の服用開始後、数週間から数ヶ月以内に出現することが多いですが、数日後や1年以上経過してから現れるケースもあります。
患者さんから「風邪でもないのに咳が続く」という訴えがあった場合、ACE阻害薬の副作用を疑うことが重要です。対処法としては、まず原因薬剤の中止が原則となります。
- 薬剤の中止: ACE阻害薬の服用を中止すると、通常は1〜4週間以内に咳は軽快・消失します。
- 薬剤の変更: 降圧効果や臓器保護効果を維持する必要がある場合、ブラジキニンの分解に影響を与えないARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)への変更が第一選択となります。ARBはACE阻害薬と同様にRAA系を抑制しますが、作用点が異なるため空咳の副作用はほとんど起こりません。
- 対症療法(非推奨): 鎮咳薬(咳止め)の効果は限定的であり、根本的な解決にはなりません。安易な対症療法は原因の特定を遅らせる可能性があるため、推奨されません。
稀ではありますが、非常に重篤な副作用として「血管性浮腫(クインケ浮腫)」があります。これは、唇、まぶた、舌、喉などが突然腫れ上がるもので、気道が閉塞すると生命に関わる危険な状態です。これもブラジキニンの蓄積が関与していると考えられており、発現頻度は低いものの、医療従事者は常に念頭に置いておくべき副作用です。
参考情報:医薬品の副作用に関する情報提供
医薬品医療機器総合機構(PMDA) – 副作用が疑われる場合の報告のお願い
ACE阻害薬とARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)の使い分け
高血圧治療において、ACE阻害薬とARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)は、ともにレニン・アンジオテンシン(RAA)系を抑制する薬剤として重要な位置を占めています。両者は似たような効果を持つ一方で、作用機序と副作用のプロファイルに明確な違いがあり、患者さんの状態に応じた適切な使い分けが求められます。
作用点の違いがもたらす効果の違い
両者の最も大きな違いは、RAA系のどこをブロックするかにあります。
- ACE阻害薬: アンジオテンシンIからアンジオテンシンIIへの「産生」を阻害します。同時にブラジキニンの分解も抑制します。
- ARB: 産生されたアンジオテンシンIIが、その受け皿である「AT1受容体」に結合するのをブロックします。ブラジキニンの代謝には直接影響しません。
ACE阻害薬のメリット: ブラジキニンの分解を抑制することで、血管拡張作用の増強や、組織修復に関わる良い効果(心保護作用など)が期待できるとされています。心筋梗塞後の患者さんに対する予後改善効果のエビデンスは、ARBよりも古くから豊富に蓄積されています。
ARBのメリット: アンジオテンシンIIの作用を選択的にAT1受容体でブロックするため、空咳の副作用がほとんどありません。また、ブロックされなかったアンジオテンシンIIがAT2受容体を刺激することによる、血管拡張や細胞増殖抑制などの有益な作用も期待されています。
臨床現場での使い分けのポイント
実際の臨床現場では、どのような基準で両者を使い分けているのでしょうか。
| ACE阻害薬が優先される場合 | ARBが優先される場合 | |
|---|---|---|
| 適応疾患 | 心筋梗塞後、心不全(特に左室収縮能が低下している症例)、エビデンスを重視する場合 | ACE阻害薬で空咳が出た場合、忍容性を重視する場合、脳卒中既往のある高血圧 |
| 副作用 | 空咳のリスクを許容できる、あるいは出現しなかった場合 | 空咳が問題となる場合、高齢者などで副作用を避けたい場合 |
| エビデンス | HOPE試験、EUROPA試験など、心血管イベント抑制に関する大規模臨床試験のエビデンスが豊富 | LIFE試験、VALUE試験など、ACE阻害薬に劣らない大規模臨床試験の結果が多数報告されている |
| その他 | 薬価が比較的安い傾向にある | 新しい薬剤が多く、1日1回投与で効果が安定しているものが多い |
結論として、両薬剤に優劣をつけることは困難です。心筋梗塞後などの特定の病態ではACE阻害薬が長年の実績を持ちますが、忍容性の高さからARBが第一選択となるケースも非常に増えています。
重要なのは、それぞれの薬剤の特性を深く理解し、目の前の患者さん一人ひとりの年齢、合併症、ライフスタイル、そして副作用の有無を考慮して、最適な一剤を選択することです。
論文引用:The Heart Outcomes Prevention Evaluation Study Investigators. Effects of an angiotensin-converting-enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. N Engl J Med. 2000 Jan 20;342(3):145-53. (HOPE試験)
ACE阻害薬が効きにくい?効果減弱の意外な要因と対策
ACE阻害薬は多くの高血圧患者さんで有効ですが、中には「期待したほど血圧が下がらない」「最初は効いていたのに、だんだん効果が弱まってきた」というケースに遭遇することがあります。これは「効果減弱」や「耐性」と呼ばれる現象で、その背景には意外な要因が隠れていることがあります。
“エスケープ現象”という落とし穴
ACE阻害薬の効果減弱のメカニズムとして、「アンジオテンシンIIエスケープ現象」が知られています。これは、ACE阻害薬によってアンジオテンシンIIの主要な産生経路(ACE経路)がブロックされても、他の経路(非ACE経路)を使ってアンジオテンシンIIが産生されてしまう現象です。
- キマーゼ経路: 心臓や血管壁には、キマーゼという別の酵素が存在し、ACEを介さずにアンジオテンシンIIを産生することができます。ACE阻害薬を長期に使用していると、このバイパス経路が活性化し、結果的に血圧が再上昇することがあります。
- 現象の確認: この現象が起きているかどうかを直接測定することは難しいですが、ACE阻害薬を増量しても降圧効果が頭打ちになる場合、エスケープ現象の可能性を考慮します。
このエスケープ現象は、ACE阻害薬の限界の一つとも言え、ARB(アンジオテンシンII受容体拮抗薬)が開発された背景の一つにもなっています。ARBはアンジオテンシンIIがどの経路で作られようとも、最終的に受容体に結合する段階でブロックするため、理論上はこのエスケープ現象の影響を受けません。
食生活や併用薬との相互作用
薬剤そのものの問題だけでなく、患者さんの生活習慣も効果に大きく影響します。
- 塩分過多の食事🧂: 食塩を過剰に摂取すると、体液量が増加し、レニン・アンジオテンシン系の活性が抑制されがちになります。RAA系が抑制された状態の「塩分感受性高血圧」では、RAA系に作用するACE阻害薬の効果は相対的に弱くなります。減塩指導は薬物治療の効果を最大限に引き出すために不可欠です。
- NSAIDs(非ステロイド性抗炎症薬)との併用💊: 関節痛などでロキソプロフェンやイブプロフェンなどのNSAIDsを常用している場合、注意が必要です。NSAIDsは、腎臓でのプロスタグランジン産生を抑制します。プロスタグランジンには血管拡張作用やナトリウム排泄作用があるため、これが抑制されるとACE阻害薬の降圧効果が減弱することがあります。特に腎機能が低下している高齢者では、急性腎障害のリスクも高まるため、併用には細心の注意が求められます。
- 甘草(グリチルリチン)の摂取: 漢方薬や一部の食品に含まれる甘草(グリチルリチン)は、偽アルドステロン症を引き起こし、カリウムの喪失とナトリウム・水分の貯留を招きます。これにより血圧が上昇し、ACE阻害薬の効果を打ち消してしまうことがあります。
効果減弱への対策
ACE阻害薬の効果が不十分な場合、以下のような対策を検討します。
- 生活習慣の再評価: まずは減塩指導を徹底し、NSAIDsや甘草など、効果を減弱させる可能性のある薬剤や食品を摂取していないか確認します。
- 薬剤の変更・追加:
- 利尿薬の併用: 塩分感受性高血圧が疑われる場合、サイアザイド系利尿薬の少量併用は非常に有効です。体内の過剰なナトリウムを排泄することで、ACE阻害薬の効果を高めることができます。
- ARBへの変更: エスケープ現象が強く疑われる場合や、副作用でACE阻害薬が使えない場合には、ARBへの切り替えを検討します。
- カルシウム拮抗薬の併用: 作用機序の異なるカルシウム拮抗薬を組み合わせることで、相加・相乗的な降圧効果が期待できます。
ACE阻害薬の効果が弱いと感じた際には、単に「効かない薬」と判断するのではなく、その背後にあるメカニズムや患者さんの生活背景を多角的に評価し、適切な対策を講じることが、より良い血圧コントロールへの鍵となります。
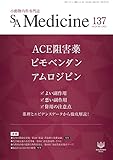
SA Medicine 2022/2月号(No.137) (ACE阻害薬,ピモベンダン,アムロジピン)
