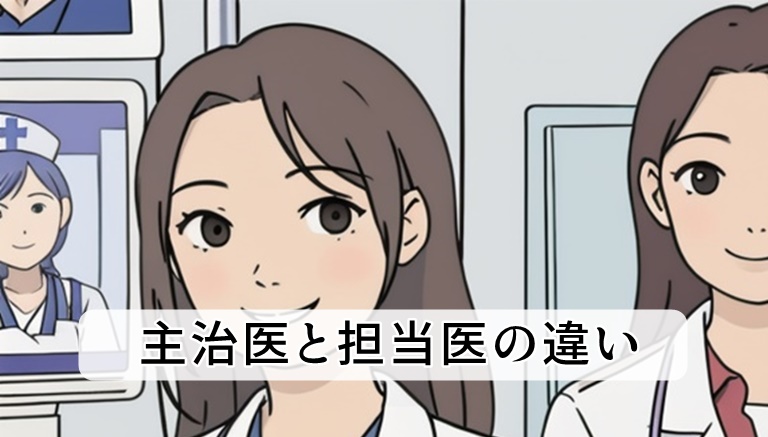
主治医と担当医の違い
主治医と担当医は、どちらも患者の診療を担当する医師ですが、その役割や責任の範囲には違いがあります。
主治医
主治医とは、患者の疾患の診療方針全般に対して主たる責任を有する医師のことです。患者の病状や治療の進捗状況を把握し、治療方針を決定・調整する役割を担います。また、患者の精神面のケアや、他の医師との連携なども行います。
複数の医師をまとめるリーダー的な立場ですね。
主治医は、原則として治療が終わるまで変わることがありません。そのため、患者は主治医に自分の病状や治療について、いつでも相談することができます。
担当医
担当医とは、主治医が率いるチームの一員として患者を治療する医師のことです。主治医の指示に従って、患者の診療や検査、治療などを行います。
担当医は、治療ごとに異なるケースがあったり、複数の医師が治療を担当したりするケースもあるため、変わることもあります。
主治医と担当医の違い
主治医と担当医の違いは、以下のとおりです。
| 項目 | 主治医 | 担当医 |
|---|---|---|
| 役割 | 疾患の診療方針全般の決定・調整、患者の精神面のケア、他の医師との連携 | 診療や検査、治療の実施 |
| 責任の範囲 | 患者の全般的な健康状態 | 患者の治療 |
| 変更の可能性 | 原則としてなし | あり |
なお、主治医と担当医を兼任する医師もいます。
主治医の役割
主治医は患者さんの治療全体を統括する立場にあります。例えば、がん治療の場合、主治医は手術の必要性を判断し、抗がん剤治療を行うか放射線治療を選択するかといった重要な治療方針を決定します。また、患者さんの状態が思わしくない場合には、循環器内科や呼吸器内科など、他の診療科の専門医への紹介を判断することも主治医の重要な役割です。
担当医の役割
担当医は主治医の指示のもと、日々の診療を担当します。朝の回診で患者さんの状態を確認し、必要な検査の実施や投薬の調整を行います。例えば、手術後の患者さんであれば、傷の状態を確認し、痛み止めの調整や点滴の管理を行います。また、血液検査の結果説明や、患者さんやご家族からの日常的な相談にも対応します。
診療における連携
実際の診療では、主治医と担当医が密接に連携しながら治療を進めていきます。例えば、入院患者さんの場合、担当医が毎日の診察で得た情報を主治医に報告し、その内容をもとに主治医が治療方針の微調整を行います。患者さんの容態が急変した場合は、まず担当医が対応し、状況に応じて主治医に連絡を取り、指示を仰ぎます。
夜間や休日の対応は、通常当直医が担当しますが、重要な判断が必要な場合には主治医に連絡が入り、適切な指示を出す体制が整えられています。このように、複数の医師が役割分担をしながら、患者さんに最適な医療を提供できるよう努めています。
違いをわかってもらうと、患者さんにこんなメリットがある
主治医と担当医の違いを理解してもらうことで、以下のような利点が患者さんにもたらされます。
診療体制の理解による安心感
主治医は患者の治療全体に責任を持ち、担当医は主治医の指示のもとで日々の診療にあたります。この関係を理解することで、複数の医師による診療を受ける際の不安が軽減されます。
適切な相談先の選択
症状や相談内容による使い分け
- 日常的な症状や投薬に関する相談は担当医に
- 治療方針の変更など重要な判断が必要な場合は主治医に相談
継続的な医療の確保
入院中は担当医が主として対応しますが、診療方針は主治医と担当医が合議のうえで決定されます。このため、一貫性のある治療を受けることができます。
医療サービスの効率的な利用
夜間や休日は回診担当医が必要に応じて対応するなど、柔軟な診療体制があることを理解することで、緊急時でも適切な医療サービスを受けることができます。
医師との良好な関係構築
それぞれの医師の役割を理解することで、適切なコミュニケーションが可能となり、より良好な医師-患者関係を築くことができます。このことは、治療効果の向上にもつながります。