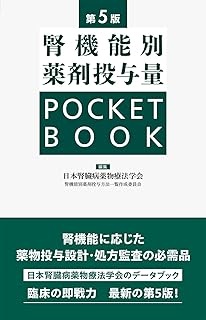術後感染予防抗菌薬の適正使用について
術後感染予防抗菌薬の目的とSSI予防の重要性
術後感染予防抗菌薬の主な目的は、手術部位感染(Surgical Site Infection: SSI)の予防です。SSIは手術後の合併症として最も頻度が高く、患者の回復を遅らせるだけでなく、入院期間の延長や医療費の増加にもつながります。
予防抗菌薬の適正使用によって達成できる効果は多岐にわたります。
- SSIの発生率低減
- 耐性菌出現の抑制
- 抗菌薬による副作用の防止
- 入院期間の短縮
- 医療コストの削減
日本化学療法学会と日本外科感染症学会が共同で作成した「術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン」では、術後感染予防抗菌薬の目的はSSIの予防であり、遠隔部位感染を含むSSI以外の術後感染性合併症は対象としていないことが明記されています。つまり、予防抗菌薬は手術創部の感染予防に特化したものであり、肺炎や尿路感染症などの他の感染症予防を目的としていません。
重要なのは、SSI予防のためには抗菌薬の使用だけでなく、適切な手術手技、術前の患者準備(除毛や皮膚消毒など)、手術環境の整備など、総合的なアプローチが必要であるという点です。予防抗菌薬はその一部に過ぎないことを認識しておく必要があります。
術後感染予防抗菌薬の選択基準と常在細菌叢への対応
予防抗菌薬を選択する際の最も重要な基準は、「手術部位の常在細菌叢に抗菌活性を有する薬剤を選択する」ということです。これは、SSIの原因となる可能性が高い細菌を予め抑制するという考え方に基づいています。
予防抗菌薬選択の基本原則は以下の通りです。
- 手術部位の常在細菌叢をターゲットにする。
- 広域スペクトラムを有する抗菌薬は使用しない。
- 必要以上に広いスペクトラムの抗菌薬を使用すると、耐性菌の出現リスクが高まる
- 必要最小限の抗菌スペクトラムを持つ薬剤を選択する
- 特殊な状況への対応。
具体的な抗菌薬の選択は手術の種類によって異なりますが、多くの清潔手術(整形外科や脳神経外科など)ではセファゾリン(CEZ)が第一選択とされています。消化器外科手術など汚染リスクの高い手術では、嫌気性菌もカバーするセファメジンやフロモキセフなどが選択されることが多いです。
重要なのは、予防抗菌薬は治療用抗菌薬とは異なる目的で使用されるため、選択基準も異なるという点です。予防抗菌薬は「これから起こるかもしれない感染を予防する」ために使用するものであり、既に存在する感染症の治療を目的としていません。
術後感染予防抗菌薬の投与タイミングと追加投与の必要性
予防抗菌薬の効果を最大化するためには、適切な投与タイミングが極めて重要です。手術切開時に手術部位の組織および血液中に十分な抗菌薬濃度が確保されていることが、SSI予防の鍵となります。
初回投与のタイミング。
- 原則として手術切開の30分前までに投与を完了する
- バンコマイシンやフルオロキノロン系薬は、投与に時間がかかるため、切開の60~120分前に投与開始する
- 投与タイミングが早すぎても遅すぎても効果が減弱する
術中の追加投与。
手術時間が長くなると、組織中の抗菌薬濃度が低下するため、追加投与が必要になります。追加投与のタイミングは抗菌薬の半減期の2倍を目安とします。
- セファゾリン:3~4時間ごと
- セフメタゾール:2~3時間ごと
- バンコマイシン:6~12時間ごと
また、大量出血(1,500mL以上)がある場合も、血中濃度が低下するため追加投与が必要です。
投与期間。
予防抗菌薬の投与期間については、多くの場合、手術当日(24時間以内)で終了することが推奨されています。長期間の投与は耐性菌出現のリスクを高め、かつSSI予防効果の上乗せがないことが多くの研究で示されています。
ただし、一部の手術(心臓血管外科や人工物挿入を伴う整形外科手術など)では、48~72時間の投与が認められる場合もあります。しかし、72時間を超える投与は、特別な理由がない限り避けるべきとされています。
実際の臨床現場では、「念のため」という理由で予防抗菌薬が長期間投与されることがありますが、これは耐性菌出現のリスクを高めるだけでなく、医療コストの増加や副作用リスクの上昇にもつながります。ガイドラインに基づいた適切な投与期間の遵守が重要です。
術後感染予防抗菌薬と創分類に基づく適応判断
手術創の汚染度に基づく創分類は、予防抗菌薬の適応を判断する上で重要な指標となります。創分類は以下の4つに分けられます。
- 清潔創(Class I)。
- 非感染性、炎症なし
- 呼吸器、消化器、泌尿生殖器の非感染性開放なし
- 無菌的に閉鎖
- 例:心臓手術、整形外科手術など
- 準清潔創(Class II)。
- 呼吸器、消化器、泌尿生殖器の管理された開放あり
- 例:胆嚢摘出術、虫垂切除術(非穿孔性)など
- 汚染創(Class III)。
- 不潔/感染創(Class IV)。
- 既に感染が成立している
- 例:穿孔性腹膜炎、膿瘍切開排膿など
予防抗菌薬の適応は創分類によって異なります。
- 清潔創:人工物挿入や感染リスクが高い手術(心臓手術など)では予防抗菌薬が推奨される
- 準清潔創:ほとんどの場合、予防抗菌薬が推奨される
- 汚染創・不潔/感染創:予防ではなく「治療的」抗菌薬投与が必要
特に注意すべき点として、不潔/感染創の場合は「予防抗菌薬」という概念ではなく、既に感染が成立しているため「治療的抗菌薬」として適切な抗菌薬を選択し、十分な期間投与する必要があります。
また、同じ手術でも患者の状態(糖尿病、免疫抑制状態、高齢など)によって感染リスクが異なるため、個々の患者のリスク因子を考慮した上で予防抗菌薬の適応を判断することが重要です。
術後感染予防抗菌薬の適正使用における薬剤師の役割と介入効果
近年、術後感染予防抗菌薬の適正使用において、薬剤師の積極的な関与が重要視されています。薬剤師は抗菌薬の専門知識を活かし、以下のような役割を担うことができます。
- 処方提案と用法用量調整。
- 患者の腎機能や体重に応じた用量調整
- 手術時間に応じた追加投与のタイミング提案
- アレルギー歴に基づく代替薬の提案
- ガイドラインに基づく標準化。
- クリニカルパスへの予防抗菌薬の組み込み
- 電子カルテシステムを活用した処方支援
- 投与期間の適正化支援
- モニタリングと評価。
- 予防抗菌薬使用の適正割合の評価
- SSI発生率のモニタリング
- 耐性菌発現状況の監視
実際に、薬剤師の介入効果を示す研究結果も報告されています。日本外科感染症学会誌に掲載された研究では、病棟薬剤師が電子カルテ上で主治医・手術室看護師に処方提案を行う介入を開始した結果、予防抗菌薬適正使用割合が介入前の62.0%から介入後は87.4%に有意に改善したことが報告されています。特に腎機能低下患者や過体重患者において顕著な改善が見られました。
また、薬剤師が中心となって病院全体を対象とした予防抗菌薬適正使用プロジェクトを実施した施設では、緑膿菌やMRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)の分離状況が改善したという報告もあります。
このように、薬剤師は抗菌薬適正使用支援チーム(Antimicrobial Stewardship Team: AST)の一員として、予防抗菌薬の適正使用推進に重要な役割を果たしています。医師、看護師、薬剤師などの多職種が連携することで、より効果的な予防抗菌薬の適正使用が実現できるでしょう。
術後感染予防抗菌薬の実践ガイドラインと各科特有の考慮点
日本化学療法学会と日本外科感染症学会が共同で作成した「術後感染予防抗菌薬適正使用のための実践ガイドライン」は、2016年に発表され、その後2020年には脳神経外科および眼科に関する追補版も発表されています。このガイドラインは、日本の医療環境に即した実践的な内容となっており、各診療科の特性に応じた推奨が盛り込まれています。
各診療科特有の考慮点をいくつか紹介します。
脳神経外科。
脳神経外科手術での主たる感染原因菌は皮膚常在菌である黄色ブドウ球菌、連鎖球菌であり、これらをカバーする抗菌薬の予防的投与が推奨されます。開頭術では、抗菌薬の使用によって術後の髄膜炎発症が有意に減少することがメタ解析やsystematic reviewによって示されています。特筆すべきは、グラム陰性菌をカバーする必要性は低く、セファゾリン(CEZ)の使用は第3世代セフェム系など他の抗菌薬と同等かそれ以上の効果があることが示されている点です。
整形外科。
整形外科手術、特に人工関節置換術では、インプラント関連感染(PJI: Periprosthetic Joint Infection)の予防が重要です。皮膚常在菌(特にコアグラーゼ陰性ブドウ球菌や黄色ブドウ球菌)をターゲットとした予防抗菌薬が選択されます。近年、MRSA保菌者に対するバンコマイシンの予防的使用や、セファゾリンとバンコマイシンの併用療法の有効性も検討されています。
消化器外科。
消化器外科手術では、手術部位によって汚染度が大きく異なるため、創分類に応じた抗菌薬選択が特に重要です。上部消化管手術では主にグラム陽性菌をターゲットとしますが、下部消化管手術では嫌気性菌を含むグラム陰性菌もカバーする必要があります。また、胆道系手術では胆汁培養結果に応じた抗菌薬選択が重要となる場合があります。
心臓血管外科。
心臓血管外科手術、特に人工弁置換術や人工血管置換術では、感染が発生した場合の重篤性を考慮して、予防抗菌薬の投与期間が他の領域よりも長く設定されることがあります(48~72時間)。また、バンコマイシンの予防的使用についても、MRSA保菌率や施設の感染状況に応じて検討されています。
各診療科の特性を理解し、それぞれの手術に適した予防抗菌薬を選択することが、SSI予防の効果を最大化し、耐性菌発現のリスクを最小化するために重要です。ガイドラインは基本的な指針を示すものであり、個々の患者の状態や施設の特性に応