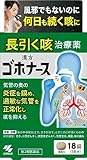肺炎で夜だけ熱が出る原因と対処法
肺炎で夜だけ熱が上がるメカнизムと原因となる病気
夜になると熱が上がる、という経験は誰にでもあるかもしれません。実は、私たちの体温は一日の中でも一定ではなく、朝が最も低く、夕方から夜にかけてピークに達するというリズムを持っています 。これは「サーカディアンリズム(概日リズム)」と呼ばれる生体リズムによるもので、自律神経やホルモンの働きによってコントロールされています 。
肺炎などの感染症にかかると、体はウイルスや細菌と戦うために免疫システムを活性化させます。この過程で「サイトカイン」という物質が放出され、体温を上げる指令が脳の視床下部にある体温調節中枢に送られます。炎症反応を抑える働きのあるホルモン「コルチゾール」は、朝に分泌が多く夜に少なくなるため、夜間は炎症が強まり、熱が上がりやすくなるのです 。
夜だけ熱が出る場合、考えられる病気はいくつかあります。
- 風邪・急性上気道炎:最も一般的な原因です 。ウイルス感染により、喉の痛みや咳、鼻水などの症状と共に発熱します。
- マイコプラズマ肺炎:特に若い世代に多く見られる肺炎で、乾いた咳が長く続くのが特徴です 。熱は微熱から高熱まで様々ですが、夜間に上がることが多いとされています。
- ヒトメタニューモウイルス感染症:乳幼児や高齢者で肺炎を引き起こすことがあるウイルスです 。熱が上がったり下がったりを繰り返す「間欠熱」が特徴的な症状の一つです。
- 溶連菌感染症:喉の痛みが強く、発疹を伴うこともあります 。迅速な診断と抗菌薬による治療が必要です。
これらの病気は、いずれも初期症状が似ているため、自己判断は禁物です。特に咳が長引く、呼吸が苦しいといった症状がある場合は、肺炎の可能性を疑い、早めに医療機関を受診することが大切です 。
肺炎による夜間の発熱と咳への具体的な対処法
夜間の発熱や咳は体力を消耗させ、睡眠を妨げるつらい症状です。少しでも快適に過ごすために、家庭でできる対処法をいくつかご紹介します。
🌡️ 安静と保温
まずは体をゆっくり休めることが第一です。厚着をしすぎると熱がこもってしまうため、汗をかいたらこまめに着替え、体を冷やさないようにしましょう。布団はかけすぎず、快適な温度を保つことが大切です。
💧 水分補給
発熱すると汗をかき、体から水分が失われがちです。脱水症状を防ぐために、こまめに水分を補給しましょう 。経口補水液やスポーツドリンクは、水分と電解質を効率よく補給できるのでおすすめです。温かい飲み物は喉を潤し、咳を和らげる効果も期待できます 。
💨 加湿と換気
空気が乾燥していると、喉や気管支を刺激し、咳が悪化することがあります 。加湿器を使ったり、濡れタオルを干したりして、部屋の湿度を50~60%程度に保ちましょう。また、定期的に窓を開けて空気を入れ替えることも大切です。
😷 マスクの着用
特に夜間のマスク着用は、喉の乾燥を防ぎ、咳の悪化を抑えるのに効果的です 。自分の呼気で喉が保湿され、冷たい空気の刺激を和らげることができます。
🧊 冷却
高熱でつらい時は、首の付け根、脇の下、足の付け根など、太い動脈が通っている場所を冷やすと、効率よく熱を下げることができます 。ただし、寒気を感じる時に冷やすのは逆効果なので、本人が気持ち良いと感じる範囲で行いましょう。
💊 解熱剤の使用
高熱で眠れない、食事がとれないなど、つらい症状がある場合は、医師の指示に従って解熱剤を使用するのも一つの方法です 。ただし、解熱剤は病気そのものを治すわけではありません。あくまで症状を和らげるための対症療法であることを理解しておきましょう。
症状緩和のための工夫について、以下のリンクも参考にしてください。
高熱と激しい咳が続く時 肺炎のサインかもしれません – 神戸の岸田クリニック
肺炎の夜間熱、子供や高齢者における特有の症状と注意点
子供や高齢者は、成人と比べて免疫機能が未熟であったり、低下していたりするため、肺炎が重症化しやすく、特に注意が必要です。また、症状の現れ方が典型的でないことも少なくありません 。
👶 子供の場合
子供、特に乳幼児は、自分で症状をうまく伝えることができません。そのため、保護者が注意深く様子を観察することが重要です。
- 機嫌が悪い、ぐったりしている
- ミルクや母乳の飲みが悪い
- 顔色が悪い、唇が紫色になっている(チアノーゼ)
- 呼吸が速い、肩で息をしている、小鼻がぴくぴくする
- ゼーゼー、ヒューヒューという呼吸音がする
熱があっても咳があまり出なかったり、逆に咳だけが続いて熱は出なかったりすることもあります。いつもと様子が違うと感じたら、早めに小児科を受診しましょう 。
👵 高齢者の場合
高齢者は、加齢に伴い体の反応が鈍くなるため、高熱が出にくい傾向があります 。そのため、肺炎にかかっていても、微熱程度だったり、熱が全く出なかったりすることもあります。典型的な呼吸器症状よりも、以下のような全身症状が前面に出ることが特徴です。
- なんとなく元気がない、食欲がない
- 意識がはっきりしない、ぼんやりしている
- 失禁する
- 脱水症状
これらの症状は「歳のせい」と見過ごされがちですが、実は肺炎のサインである可能性があります。普段から本人の様子をよく知る家族や介護者が、ささいな変化に気づくことが早期発見につながります。
以下の表は、子供と高齢者の肺炎で特に注意すべき点をまとめたものです 。
| 対象 | 特徴的な症状 | 注意すべき点 |
|---|---|---|
| 子供 | 機嫌が悪い、ぐったりしている、ミルクを飲まない、顔色が悪い、呼吸が速い、ゼーゼーする、発熱があっても咳があまり出ないことがある
|
症状が急変しやすいため、少しでも異変を感じたら速やかに医療機関を受診する必要があります 。 |
| 高齢者 | 元気がない、食欲がない、意識がはっきりしない、失禁するなど、呼吸器症状以外の症状が目立つことがある
参考)高齢者の発熱対応で特に気をつけるべきことを教えてください。 … 。発熱しないことも多い 。 |
症状が非定型的で気づきにくいですが、重症化しやすいため、普段と違う様子が見られたら早めに医師に相談することが重要です。 |
子供や高齢者の肺炎予防には、インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンの接種が有効です 。また、日頃からの手洗いやうがい、規則正しい生活を心がけ、免疫力を高めておくことも大切です 。
肺炎の夜間発熱時に病院を受診するタイミングと治療法
夜間に熱が出ると、救急外来を受診すべきか迷うこともあるでしょう。しかし、すべての発熱で夜間救急を受診する必要はありません。受診のタイミングを見極めるためのポイントを解説します。
🏥 すぐに受診すべき症状
以下の症状が見られる場合は、肺炎が重症化している可能性や、他の重篤な病気が隠れている可能性があるため、夜間や休日であっても速やかに医療機関を受診してください 。
- 呼吸が苦しい、息切れがする
- 肩を上下させて、努力しないと呼吸ができない
- 唇や顔色が悪く、紫色になっている(チアノーゼ)
- 意識が朦朧としている、呼びかけに反応しない
- 水分が全く摂れず、ぐったりしている
特に子供や高齢者は、症状の進行が早いことがあるため、ためらわずに救急要請も検討してください 。
🩺 翌日の日中に受診を検討するケース
上記の緊急性の高い症状がなく、全身状態が比較的良好な場合は、翌日の日中に近くのクリニックを受診するのでも間に合うことが多いです。ただし、以下のような場合は、早めの受診をおすすめします。
🔬 病院での検査と治療
病院では、まず問診や聴診、血圧測定などを行い、全身の状態を評価します。肺炎が疑われる場合は、胸部X線検査や血液検査、喀痰検査などを行い、診断を確定します 。
肺炎の治療は、原因となる病原体によって異なります。
- 細菌性肺炎:原因菌に合わせた抗菌薬(抗生物質)を投与します。
- ウイルス性肺炎:インフルエンザなど一部のウイルスには抗ウイルス薬がありますが、多くは対症療法が中心となります。
- 非定型肺炎(マイコプラズマなど):マクロライド系などの特定の抗菌薬が有効です 。
治療は主に内服薬で行いますが、重症の場合は入院して点滴治療や酸素吸入が必要になることもあります。医師の指示に従い、処方された薬はきちんと飲み切ることが大切です。
肺炎とストレスの意外な関係?心因性発熱という独自視点
「夜だけ熱が出る」という症状が続くものの、検査をしても肺炎や他の感染症が見つからない場合があります。そのような場合に考えられるのが「心因性発熱」です 。これは、精神的なストレスが原因で体温が上昇する状態で、一種の自律神経失調症とも言えます。
私たちの体は、強いストレスを感じると、交感神経が活発になります。交感神経は、心拍数を上げたり、血管を収縮させたりして、体を「戦闘モード」にする働きがありますが、同時に体温を上昇させる作用も持っています 。通常であれば、ストレスから解放されると体温は元に戻ります。しかし、慢性的なストレスにさらされていると、自律神経のバランスが乱れ、体温調節機能がうまく働かなくなり、微熱や高熱が続くことがあります。
🤔 心因性発熱の特徴
- ストレスとの関連:仕事や人間関係の悩み、環境の変化など、特定のストレスがかかった時に発熱したり、症状が悪化したりする傾向があります。
- 解熱剤が効きにくい:心因性発熱は、炎症による発熱とはメカニズムが異なるため、一般的な解熱鎮痛薬(NSAIDsなど)が効きにくいという特徴があります 。
- 他の身体症状:頭痛、倦怠感、動悸、めまい、不眠など、自律神経失調症に伴う様々な症状を伴うことがあります。
肺炎などの感染症による発熱は、体力を消耗させ、精神的なストレスにもつながります。病気が治った後も、なかなか熱が下がらない、あるいは微熱が続くといった場合、もしかしたらその発熱は、病気そのものではなく、病気を経験したことによるストレスが引き起こしているのかもしれません。
「病は気から」ということわざがありますが、心と体は密接につながっています。もし、長引く発熱の原因が分からず、日常生活で強いストレスを感じているのであれば、一度、心療内科や精神科に相談してみるのも一つの選択肢です 。原因となっているストレスを特定し、カウンセリングや薬物療法を通じて心の負担を軽くすることが、解熱への一番の近道になる可能性があります。
心因性発熱に関する詳しい情報は、以下の専門サイトでも確認できます。
「夜だけ熱が出る」のは「マイコプラズマ肺炎」や「関節リウマチ」が原因? – Medical DOC